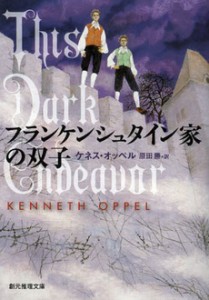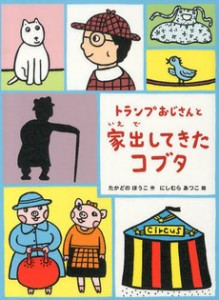橋下大阪市長の従軍慰安婦に対する発言が物議をかもしていますが、私は彼が使う「活用」という言葉が、彼の女性に対する考え方を語っているように思います。性は、人が人として生きていく根幹にある、自己の尊厳と不可避に結びついているもので、決して人に「活用」されてはならないものなのです。彼は、そういうことがわからない人なのでしょう。でも、今の日本では、こうして「おかしい」と思ったことについて発言も議論も出来ますが、もし政治に対して何も言えなくなってしまったときに、彼のような人間がトップに座ってしまったら―そう思うと非常に恐ろしい。この『スターリンの鼻がおっこちた』は、スターリン時代のソ連の少年が経験した恐怖の物語です。全く他人事ではない恐怖が目の前に迫ってくる迫力に満ち溢れています。
橋下大阪市長の従軍慰安婦に対する発言が物議をかもしていますが、私は彼が使う「活用」という言葉が、彼の女性に対する考え方を語っているように思います。性は、人が人として生きていく根幹にある、自己の尊厳と不可避に結びついているもので、決して人に「活用」されてはならないものなのです。彼は、そういうことがわからない人なのでしょう。でも、今の日本では、こうして「おかしい」と思ったことについて発言も議論も出来ますが、もし政治に対して何も言えなくなってしまったときに、彼のような人間がトップに座ってしまったら―そう思うと非常に恐ろしい。この『スターリンの鼻がおっこちた』は、スターリン時代のソ連の少年が経験した恐怖の物語です。全く他人事ではない恐怖が目の前に迫ってくる迫力に満ち溢れています。
子どもは、一番強く時代の影響を受ける存在です。子どもは自分の弱さをよく知っています。そして、大人のように思想や教育から距離を取って生きていくことはできません。この物語の主人公であるザイチクも、秘密警察の父を幹部に持つ筋金入りの共産主義者として、ピオネール団という党の少年部に入団することを楽しみにしています。ところが、入団式の前日、今度は父親が秘密警察に逮捕され、連行されてしまうのです。密告したのは隣に住む男で、ほかに家族のいないザイチクはあっという間に夜の町に放り出されてしまいます。
ソ連という国がかってあったこと。スターリンが「大粛清時代」に2000万人もの人を追放したり処刑したり、収容所送りにしたこと。この本をいきなり手にした子どもは、そんな歴史的な知識を持ち合わせないことだろうと思います。でも、冒頭の、ザイチクが書いたスターリンへの手紙に、まず衝撃を受けるはずです。衝撃を受けないまでも、その為政者に対する盲目的な「いい子」っぷりに居心地の悪さを覚えるはずです。彼にとっては秘密警察にいる父親は英雄なのです。ザイチクを取り巻く何もかもが、今の自分たちの価値観とは違うらしい。ザイチクの眼を通じて感じるその居心地の悪さは、読むに従ってますます強くなります。監視しあっているアパートの人たちの目つき。いきなり鳴らされる真夜中の呼び鈴と、階段を上がってくる軍靴の音。いきなり連れ去られる父親の背中。ザイチクは一夜にして「いい子」から人民の敵の子どもに転がり落ちてしまったのです。転がり落ちてしまったザイチクの世界は一変します。しかも、ザイチクは学校でスターリンの胸像の鼻を壊してしまうのです。ゴーゴリの『鼻』の八等官のように、自分を取り巻くすべての世界が変わってしまったのです。今や、ザイチクも「人民の敵」。ザイチクは怯えます。教室内で行われる胸像を壊した犯人探しの恐ろしいこと。しかし、恐怖はこれで終わりません。これまで馬鹿にしていた同級生のメガネがまず自分の代わりに連れて行かれ、それから密告によって担任の先生が連れていかれ・・・ザイチクは校長に自分の父親を密告することを勧められ、そのときにもっと恐ろしい秘密を教えられるのです。
ザイチクの恐怖は、過ぎ去った過去の、自分とは関係ない恐怖なのか。この本は、読み手にそう語りかけます。自分の周りに、偉そうな洋服を着た「鼻」はいないか。もしくは、自分の鼻は、勝手に歩き出したりしないか。自分が信じている価値観が、一夜にしてくるりとひっくり返ったらどうするのか。カリカチュアライズされた挿絵の迫力も相まって、手がかりのない悪意の壁に囲まれるような孤独感が怖さを倍増させます。作者のユージン・イェルチンは、ソ連生まれです。それだけに、この物語には大粛清時代の恐ろしさが生きて脈打っているようです。私がこのザイチクの立場にいたら―きっと、彼のように「いい子」してしまったような気がします。子どもの頃、大人の顔色を読むことは抜群に上手でしたから。だから、この物語は他人事ではないし、今の日本にとっても他人事ではない。この物語のスターリン主義を、「グローバル」や「実力主義」という言葉に置き換えてみることだって出来るでしょう。訳者の若林さんが後書きで書かれているように、今の日本の子どもたちの状況に通じるものがあります。今の若い人たちに要求されるグローバリズム社会への適応力は、私のようなナマケモノには辛いとしみじみ思います。若い人の能力を、安価で、根こそぎ吸いつくそうとする化け物は、カッコいい服を着た大きな鼻かもしれません。そんな鼻はメガネくんの写真を塗りつぶしたように、ひとりの人間をモノ扱いします。そんな人をモノ扱いする大人の冷たさは、子どもの社会のいじめの問題にも繋がっている気がします。ザイチクの学校での粛清の恐ろしさに、学校での孤独を重ね合わせる子どもたちもいるでしょう。
「わたしたちがだれかの考えを、正しかろうが間違っていようが、うのみにし、自分で選択するのをやめることは、遅かれ早かれ政治システム全体を崩壊に導く。国全体、世界をもだ」
粛清の嵐が吹き荒れる教室の中で、たったひとりゴーゴリの『鼻』を教え続けるルシコ先生の言葉が身に沁みます。この物語は、ニューベリー賞のオナーブックに選ばれています。子どもたちにもぜひ読んで欲しいし、大人にも新しい目を開かせる一冊だと思います。この時代に収容所に送られた人がたどった恐怖は、『灰色の地平線のかなたに』(ルータ・セペティス 岩波書店)や、実際にシベリヤで抑留生活を送った石原吉郎の著書にも詳しく書かれています。
2013年2月発行
岩波書店