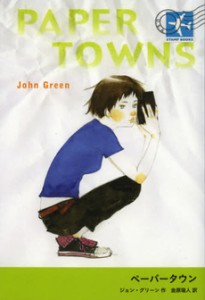性をテーマにした短編の連作です。タイトルが、ちょっと怖いもんですから、ちょっと身構えました。女の性(さが)を自分のカラダで確かめました系のめくるめく愛欲の世界・・・なんていうのは、もはや読むのがめんどくさいんですよ。でも、川上さんだから、そんなことあるはずもなく。久しぶりにずっしりと読み応えのある川上さんの濃密な言葉の世界でした。
性をテーマにした短編の連作です。タイトルが、ちょっと怖いもんですから、ちょっと身構えました。女の性(さが)を自分のカラダで確かめました系のめくるめく愛欲の世界・・・なんていうのは、もはや読むのがめんどくさいんですよ。でも、川上さんだから、そんなことあるはずもなく。久しぶりにずっしりと読み応えのある川上さんの濃密な言葉の世界でした。
「aqua」「terra」「aer」「ignis」「mundus」という五つの短編が並んでいます。少女時代から時系列に並べられている形なんですが、川上さんなので、そんなに簡単に読み解けるしろものではありません。(うふふ・・・しろもの。「aer」に出てくるこの言葉が頭を離れない)実験的に表現形式も温度も視点も変えて紡がれる小説たちが、この一冊の中でぐるぐると生と死を繰り返しているようなのです。ことに面白くなってくるのが、「aer」から後の3編。ここに「しろもの」が出てくるんですよ。しろもの、とは、赤ん坊のことです。あの妊娠・出産期という、自分が自分でなくなってしまう時間の中に流れていた濃密なもの。そう、自分も「どうぶつ」だったなあ、と。そして、あの頃にさんざん翻弄されていた赤ん坊を「しろもの」と言ってしまう川上さんの言語感覚に、強烈なカタルシスを感じてしまう。だって、あの頃私は「どうぶつ」だったのだから、自分が体の奥底に抱えていた充足と恐怖をこんな風に言葉にすることは出来なかったもの。言葉にならないことを言語化するという営みは、私たちを普遍に連れていきます。一人の少女から生まれた「性」は、たった一人で死んでいく女のつぶやきも、しろものを産んでしまって右往左往する母親の戸惑いも、女とは全く違う男という生き物との果てしない距離も、すべてを連れて旅し、どこか知らない混沌に帰っていくのです。川上さんの言葉は、「言葉」という抽象でありながら、肉体を伴って、そのまま滅びていく手ごたえがある。それがとても不思議で、魅了されます。
伊勢物語と浄瑠璃の道行をかけあわせたような「igunis」が特に面白かった。道行、というよりはお遍路さんの歩く道のイメージに近いかな。苦行のような、諦めのような(笑)もしかしたら、今の私が、この短編のどんぴしゃな年齢なのかもしれないんですが。ラストの「mundus」は、詩と散文の間を揺れ動くような、密度の濃い一篇。何度読み返しても、夥しく語られる「それ」の正体が頭の中で伸びたり縮んだり、膨れ上がったりして眩暈がします。「それ」はどこからかやってきて、どこかに去っていく私たちに刻印されている夥しい記憶なのかも。段々「それ」が何か、何て考えることもやめて、川上さんの紡ぐ言葉の川に身をゆだねて流されるままに流されました。その川は「なめらかで熱くて甘苦しくて」、どうやらたどりつくのは彼岸らしいとわかっても、そのまま流されたくなります。うん。ずーっとこうして「性」に流されてきたなあと。最後の最後でまたしても川上さんにやられた、と思う、そんな一冊でした。
2013年2月刊行
新潮社