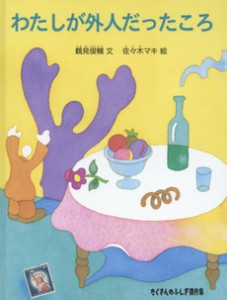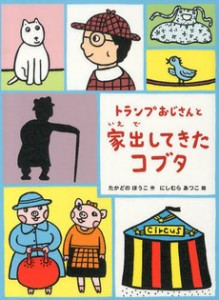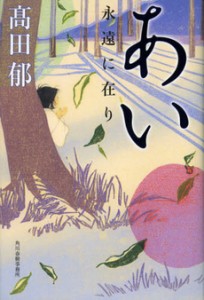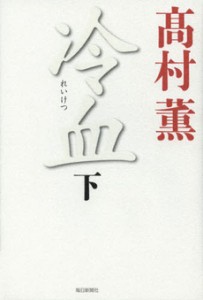国とは何だろう。国という大きな枠組みに属してい ないと、わたしたちが人間らしく生きることは難しい。しかし、「国」というアイデンティティは、私たちを形作る複雑な、無数の要素のたった一つにすぎないはず。好きな音楽、食べ物の好み、どんな家に住み、どんな仕事をしているのか。映画の好みや、それこそ推しのアイドルに至るまで、ひとりの人間のなかには、無数のアイデンティティがある。それなのに、たった一つ、国という帰属のために、敵と味方に分かれて殺しあわねばならぬという価値観に縛られる理不尽から、そろそろ自由になってもいいはずだ。
ないと、わたしたちが人間らしく生きることは難しい。しかし、「国」というアイデンティティは、私たちを形作る複雑な、無数の要素のたった一つにすぎないはず。好きな音楽、食べ物の好み、どんな家に住み、どんな仕事をしているのか。映画の好みや、それこそ推しのアイドルに至るまで、ひとりの人間のなかには、無数のアイデンティティがある。それなのに、たった一つ、国という帰属のために、敵と味方に分かれて殺しあわねばならぬという価値観に縛られる理不尽から、そろそろ自由になってもいいはずだ。
「すべての いきものが、うまれて そだつ」という文章と生き物たちの鮮やかな絵からはじまるこの絵本は、DNAという生き物の「せっけいしょ」について、わかりやすく楽しく教えてくれる。驚くほどはやく成長するもの、長い時間をかけるもの。大きく成長するもの、小さいサイズでおとなになるもの。環境にあわせてDNAの設計書がつくりかえられ、驚くほど多様な生き物たちが、この地球上に生きているという奇跡がどのようにこの青い星に満ちているのか。その理由が科学の力でわかりはじめたからこそ、なお募る不思議さと豊かさが、ぎっしりとこの絵本には描きこまれている。
様々な肌の色、髪、体格、服装をした人たちが100人以上いる駅を描いた頁と、動物や植物たちが300種類近く(正確に数えるのが難しいほどたくさん!)も描きこまれた頁が呼応するように配置されているのは、考え抜かれてのことだろう。様々な人種に分かれているように見えるが、私たちは「人間」という大きなひとつの種だ。肌や髪の色の違いは、多様性というDNAの生存戦略。人間のDNAという設計書は、ひとりひとり違うけれども、「わたしたちは みんな おなじ、にんげんだから。」地球上のほかの人たちとも似ていること。そして、地球上のすべての生き物の設計書も、どこか同じところがあって、「みんなが おおきな かぞく」であること。大きな命の樹に実る果実のように。
見かけも、生き方もこんなに違う生き物がいる地球の不思議と、それが塩基というたった4つの文字で書かれた暗号から、出来ているんだという驚きを何度も味わいたい。科学は、積み上げられた事実に裏打ちされた大切なことを教えてくれる。動物学者であるニコラ・デイビスは、科学者の視点から、命の不思議を教えてくれるが、そこには深い祈りがあると思う。どうやら、私たち人間の遺伝子には、ある条件がそろうと発動する残虐さが組み込まれている。ゾンビのように蘇る戦争を、これほど繰り返しているのだから。しかし、この血塗られた呪いを解く鍵もやはり私たちのなかにあると思いたい。ニコラ・デイビスは、その鍵のひとつを、子どもたちに手渡したいと思っているのではないだろうか。彼の書いた『せんそうがやってきた日』(レベッカ・コップ絵、長友恵子訳、鈴木出版)という絵本もぜひ読んでほしい。もう、大人たちの憎しみに子どもたちが殺されるのは、たくさんだ。
2021年4月発行