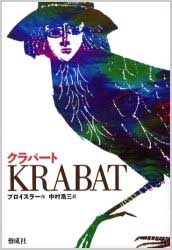 土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。
土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。
村をまわって物乞いをする貧しい生活にくたびれた14才の少年、クラバートはある日夢で彼をさそうカラスの夢を見る。その声にしたがってコーゼル湿地のほとりにある水車小屋にやってきた彼は、まるで当たり前のようにそこで働くことになる。なにしろ寝るところと食べるものがある、というだけでもクラバートにとってはありがたいことなのだ。しかし、そこはただの水車小屋ではない。親方は魔法使いで、どうやら十一人の職人は彼に魔法で縛られているらしい。それが証拠に、単調な労働に嫌気がさして逃げようとしてもどうしてもそこからは逃げられない。そして辛い見習いの期間が終わると、昼間は魔法の力でラクに働けるようになり、カラスになって親方から魔法をおそわる日々が続く。しかし、親方との恐ろしい契約は、どうやらそれだけではないらしい。なんと一年に一人職人達が死んでゆくのだ。クラバートに親切にしてくれたトンダ、そして落ち着きのあるミヒャルも死んでいく。そんな虜の生活の中で、クラバートは一人の少女と出会う。そして、この囚われた生活から彼を救い出してくれる方法は、彼女がクラバートに会いにきて、彼をえらんでくれることだということを知る。はたしてクラバートの運命は・・?
まるで終わらない夢のなかでずっと働いているようなこの物語。 読んでいる間中時間軸がずれていくような不思議な感覚に襲われました。霧の漂う湿地。カラスに変身して行われる魔術の授業。時々現れる、親方のまたその親方である男の不気味さ。彼がくる夜にひきうすですりつぶすのは、人の骨・・?!そして、一つずつ増えていく、湿地の墓と棺桶。この水車小屋での労働は、生身の身体で行うものではないらしい。みんなで働くこと自体は苦痛を伴うものではないらしい。身体も疲れないし、困ったことがあっても、ちょっと魔法を使えばうまくいってしまうし。なにしろ、この時代の一番重要な「食べること」には困らないんだから・・。でも、その代償として大きすぎるものをクラバートたちは親方に与えてしまう。それは自由と、命と、それから誰かと愛し合うこと。好きな女の子ができても、とことん黙っていろと言ったトンダは、やはり愛を親方に潰された人だった。みじろぎもしないで彼女を思うトンダとともにいる時に聞いた、どこからともなく聞こえてきた歌声。それがクラバートの愛する人・・・。すべてがモノトーンのなかにうずもれているようなこの物語の中で、この自分の可愛い人とふれあう時だけ、色づいているような美しさが溢れます。それは、語りかける声だけでかわすような恋です。でも、暖かい命そのもののような彼女の存在が、この魔術も親方の陰謀も、恐ろしい束縛も、すべてを吹き飛ばしてしまう力になる。この大いなる女性の力。
「心の奥底からはぐくまれる魔法」が解き放ったクラバートは、魔術も使えず、もう自分の力だけでいきていくことになる。でも、クラバートには、それは苦痛ではないはず。自由と愛を手にいれたんだから。そう。どうせ囚われるのなら、魔法にではなく、愛に囚われたいよなあ。
この物語は、古い民話がベースになっているらしい。やはり民話というのは、その土地がもつ、そこから生まれた幻想だけが持つ深さがあります。人が心の底に持つ、古い古い記憶の中で発酵している積み重ねられた思いは、夢の中で響く歌声のように、懐かしくて人を虜にする。
幻想を色濃く反映しながら、長い時間をかけて書かれたこの物語は、緻密な構成と筆力で、見事な幻想溢れるファンタジーになっています。それぞれのシーンが美しいんですよ。様々な光景が流れて、自分の中にしみこんでいくようです。この世界を見事に表現したヘルベルト・ホルツィングの挿し絵もこよなく魅力的。宮崎駿監督も、この物語から多くの着想を得ているそうです。
「千と千尋」のラスト、千尋が豚のなかから両親を選ぶシーンなんて、まさしくそうだなあ。魔女と契約して働く、というのもやはり同じだし。この物語と映画を比較しながら読んでも面白いかも。面白くてそんなこと忘れてよんじゃいましたが。オトナの人むけのファンタジー。とっぷり幻想の気配とゾクゾクする怖さを味わいたい人に。
by ERI
