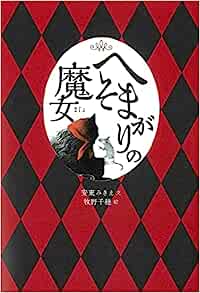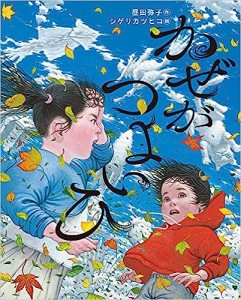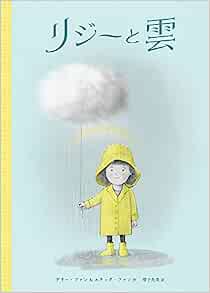昨年刊行された『ぼくは川のように話す』のコンビによる絵本。私はシドニー・スミスの絵がとても好きだ。『このまちのどこかに』(せなあいこ訳 評論社)の冬の都会の風景も忘れがたいし、『ぼくは川のように話す』の、川面のきらめく光にもとても心惹かれた。この『おばあちゃんのにわ』の表紙も、とてもいい。おばあちゃんとぼくのまわりを、うっすらと取り巻く光。まるで二人を祝福するかのようだ。シドニー・スミスの描く光には、時間と季節の表情がある。二人が朝食をとるシーンの朝の光。庭を歩く夕方の光。雨の日にガラス窓から射す淡い光。それが見事に心を映し、響いてくる。
昨年刊行された『ぼくは川のように話す』のコンビによる絵本。私はシドニー・スミスの絵がとても好きだ。『このまちのどこかに』(せなあいこ訳 評論社)の冬の都会の風景も忘れがたいし、『ぼくは川のように話す』の、川面のきらめく光にもとても心惹かれた。この『おばあちゃんのにわ』の表紙も、とてもいい。おばあちゃんとぼくのまわりを、うっすらと取り巻く光。まるで二人を祝福するかのようだ。シドニー・スミスの描く光には、時間と季節の表情がある。二人が朝食をとるシーンの朝の光。庭を歩く夕方の光。雨の日にガラス窓から射す淡い光。それが見事に心を映し、響いてくる。
作者であるジョーダン・スコットのおばあちゃんは、ポーランドからカナダに移民としてやってきた人だ。第二次世界大戦中は家族とともに、非常な苦労を味わったとのこと。第二次世界大戦は、ナチスドイツがポーランドに侵攻したとことを皮切りにはじまった。ユダヤ人に対する弾圧も、最も激しかった。有名なトレブリンカの収容所も、アウシュヴィッツの収容所もポーランドにある。ポーランドの総人口の五分の一が大戦中に亡くなっていて、大戦後はソ連の鉄のカーテンの向こうに組み込まれた。今、ロシアと戦争中のウクライナとは隣同士だ。『炎628』や『異端の鳥』という映画を見ると、当時の東欧がさらされていた暴力の恐ろしさの一端が垣間見える。垣間見えるだけで、本当のところはとてもわからない。いろんな当時の記録を何冊読んでもわからないことだらけだ。占領、飢餓、告発、逮捕、連行、病気。このおばあちゃんは、そんな苦難をかいくぐり、故郷から離れ、今は孫と一緒に、穏やかな光に包まれて歩いている。表紙のおばあちゃんの背中は、その幸せなひと時の重みを語っている。
元ニワトリ小屋だったというおばあちゃんの家が、とてもいい。朝の光に照らされて、猫がいて、いろんな果物や野菜がつるされたり、積まれたりしている。ビーツは、おばあちゃんの故郷の味だろうか。ぼくが食べ物をこぼすと、おばあちゃんはさっと拾い上げて、キスをしておわんに戻す。おばあちゃんの中にはたくさんの記憶が息づいているのだろう。言葉の壁があっても、いや、うまく言葉にできないことが、毎日の積み重ねのなかで「ぼく」に伝わっている。この穏やかさが、静かに満ちる安らぎが、実はとても尊く、得難いものであることが、繰り返して読むうちに伝わってきて、心がしんとする。過去と未来と今が、すべてこの一冊のなかで憩っているようだ。手元において、何度も開きたい絵本だ。