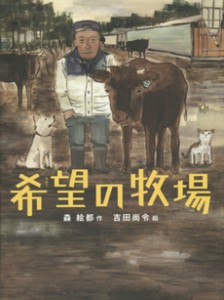昔に比べて長編を読むのが体にこたえる。若い頃と体力が違うというのもあるが、そこに描かれるひとつひとつの人生が、年齢と共に深い実感を伴って心に食い込んでくるからだ。私の体の中の時間に、この『低地』の登場人物たちの記憶がどっと流れ込んで混じり合う。既視感のような、まだ見知らぬもう一人の自分と出会っていくような、小説と自分だけが作り出すたったひとつの世界を、浮遊する数日間だった。
昔に比べて長編を読むのが体にこたえる。若い頃と体力が違うというのもあるが、そこに描かれるひとつひとつの人生が、年齢と共に深い実感を伴って心に食い込んでくるからだ。私の体の中の時間に、この『低地』の登場人物たちの記憶がどっと流れ込んで混じり合う。既視感のような、まだ見知らぬもう一人の自分と出会っていくような、小説と自分だけが作り出すたったひとつの世界を、浮遊する数日間だった。
これは、死者と生きていこうとする人間たちの闘いの物語だ。まるで双子のようにインドのカルカッタ郊外で育った兄弟と、その妻。弟のウダヤンは、若くして革命運動に身を投じ、警官に自宅の裏にある低地で射殺される。それは、身重の妻と両親の目の前でのことだった。妻のガウリの人生は、そのとき一度粉々に壊れてしまった。兄のスパシュは、彼女を妻として留学先のアメリカにつれてゆき、家族として暮らそうとするのだが、ガウリはどうしてもその暮らしに馴染むことができない。それはそうだろう。例えスパシュがどんなに優しくても、誠実な人であったとしても、彼はガウリが愛した人ではなかったのだから。一度粉々になった壺を何とかテープで貼り合わせてみても、そこには何も溜まらない。ガウリは、もう一度、今度は哲学を勉強することで自分を一から立て直してゆく。「ガウリは精神に救われていた。精神を支えにしてまっすぐ立った。精神が切り開いた道をたどっていった」のだ。しかし、それは妻であったり、母であったりすることとは全く相容れない孤独な作業なのだ。その苦しみが彼女を引き裂き、ガウリは、とうとう娘を棄てて家を出る。世間的には許されないことかもしれないが、それはガウリにとって抜き差しならない営みであったのだ。 一方、ウダヤンの死に向き合い続けたのは、スパシュも同じだ。彼にとって弟は、イデオロギーの上で反発しあったとしても、自分の分身のようなものだった。その彼の代わりに父親になろうとし、ガウリとその娘のベラを守ろうとし、ベラを心から愛した。愛情から生まれた結婚ではなくても、妻と子に精一杯誠実であろうとした。しかし、結婚生活はうまくゆかない。そう、うまくゆかないことは始めからわかっていたのだが、彼は失われた弟の人生が失われたままであることに耐えられなかったのだ。彼のとった方法は間違っていたのかもしれない。しかし、これもまた、抜き差しならない彼の、死と向き合う営みだった。そして、ガウリの娘であるベラもまた、母の失踪という喪失を常に胸の内に抱えていきてゆくのだが、不思議にその足跡は、革命に生きた実の父、ウダヤンと同じような軌道を描き出すのだ。アメリカという移民の国で、ウダヤンという一人の男の生と死を身の内に抱えた三人がたどる足跡を抑えた筆致で俯瞰していくこの物語は、過去と今をぎゅっと凝縮させたような質感に満ちていて、その人生の厚みに圧倒された。
私たちは、生きているものだけでこの社会を動かしている気になっているが、実は全くそうではない。ウダヤンを革命に突き動かしていったのは、インドの大地に踏みつけられるように殺されてゆく貧しい人々の死だった。また、ウダヤンの死は家族の運命と常に共にある。そして、ジュンパ・ラヒリはこの運命の影にある死を、もう一つ用意している。ネタバレというか、この物語を最後まで読んで得られるものを傷つけてしまうような気がするので詳しくは書かないが、それはウダヤンとガウリが正義を行おうとして夫婦で間違いを侵した結果としての死なのだ。私にはその死が、ウダヤンの死そのものよりもガウリの苦しみの最も深いところに突き刺さったまま、ガウリの心を凍らせてしまったことを感じた。だから、ガウリは母性のままに子どもを愛せないのではないか。ガウリは、被害者でもあり加害者でもあった。
「ぽつんと小さく浮いた疑惑の点、あの兄妹と座った窓辺から街路を見下ろし、もっと凶悪なことなのかもしれないと思った心の動きを、彼女は押し殺していた。」
見ないふりをした死を、ガウリは一生見つめ続けて生きてきた。ガウリは被害者であるとともに、加害者でもあった。しかし、生きることは常の二つの立場を抱えているものなのだと思う。その二つを見つめ続けたガウリの人生に、深くのめり込んで私はこの物語を読み終えた。彼女の強さも愚かさも、頑なな一途さも、まるで自分の一部であるかのようだった。
人はその体の内に、大切な「死」を抱えて生きてゆく。ウダヤンという一つの死を身の内に深く抱き続けた家族の物語は、まるで星の軌跡のように一つの宇宙を作っていく。私にはヒンドゥーの知識があまりないのだが、この物語を読んでいると、神々の列伝が語られてゆく形に近いのかもしれないと想像したりした。彼等は歴史に何の名前も残さないが、その人生は、その身に愛と罪と誇りを抱くかけがえのなさに輝いている。そのひとつひとつを、愛という腕で抱き取ってゆくラヒリの眼差しと筆力に脱帽の一冊だった。