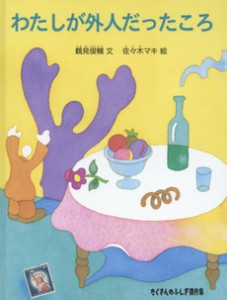
鶴見俊輔氏が93歳で亡くなられた。文章と本でしか存じ上げないのに、あんなに凄い知性の方なのに、なぜかとても心の近くに存在を感じる方だった。朝日新聞の上野千鶴子氏の追悼の文章が心に沁みる。もっと氏の本を読まねばと、憲法九条がなし崩しにされようとしている今、焦るように思っていたところだった。私の勉強の仕方は、いつも遅すぎる。
この本は、福音館書店が出している「たくさんのふしぎ」という月刊誌から生まれたもので、今年の五月に傑作集としてハードカバーで出版された。16歳だった鶴見少年がアメリカに渡り、ハーバード大学に入学する。しかし、日本とアメリカは戦争を始め、大学卒業間際だった俊輔青年は留置場に入れられてしまう。その後、「日本が戦争に負ける時、負ける国にいたい」と帰国するも、徴兵されて戦地へ。そこでカリエスを発症して帰国し、敗戦の日を迎えたのだ。この体験は、鶴見氏のその後の生き方の原点になっている。
「わたしは、アメリカにいた時、外人でした。戦争中の日本にもどると、日本人を外人と感じて毎日すごしました」
大体の日本人は、自分が「日本人」であることに、何の疑いも持たない。しかし、鶴見青年は、戦争というものによって、自分のアイデンティティを根本から覆されてしまったのだ。そして、鶴見青年を乗せた日本の軍艦は、一隻残らず太平洋に沈んでいった。たくさんの人が死んでいった。では、「なぜ自分がここにいるのか」。自分の生き残った理由もわからない。その「たよりない気分」はずっと続く。常に思想家の鶴見氏の中には、この思い惑う、柔らかな心の青年が息づいている。鶴見氏は、ずっと問いかけ続けたのだ。自分は何者か。日本人であるとはどういうことか。日本がした戦争とは何か。近代とはなにか。国とはなにか。一生をかけて問い続け、行動し、自分の頭で、考え続けた人。その原点には、自分の肉体で感じた抽象化されない強い実感がある。その実感が、ここに、とてもわかりやすい言葉で、子どもたちに向けて綴られている。佐々木マキさんの挿絵も、氏の孤独や「国家」の不気味さを写し、不思議な美しさで一人の青年の内面を表現している。
この不安や孤独に揺らいだ感覚をずっと忘れずにいたこと、魂の奥深くに刻んだことが、真のリベラルな思想を生んだのだと私は思う。だからこそ、これからを生きていく子どもたちにこの本を読んで欲しい。感じて欲しい。復刊されて良かったと心から思う。


