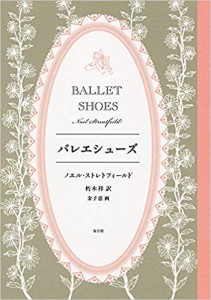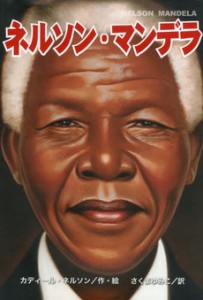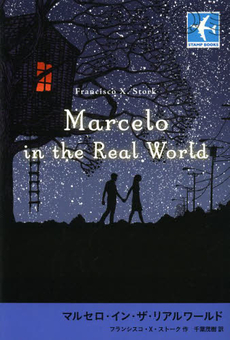窓ガラスが割れ、家族の写真も壁から落ち、一目で爆撃されたことがわかる部屋に兄と妹がいる。両親の姿はすでにない。戦車が迫る町から逃げ出さないと命があぶない。途方に暮れる幼い妹に、兄は「ぼうけんかになりたくない?」と言葉をかけ、一冊の本とともに、戦火から逃れ、難民のひとりとなって歩き続ける。生き延びるために、兄は物語の魔法の力を妹と分け合おうとした。次々と直面する苦難に打ちひしがれるたび、兄はその魔法が解けないように、妹に、これは「ぼうけんか」になるための旅だと必死に語り続ける。それは、自分をはげます魔法でもあるのだ。
「さあ、おやすみ……。/ぼうけんかには こわいものなんて なにもないんだ。/もちろん、くらやみだって」
小さな肩に背負う妹の命と、胸に抱えた悲しみ。複雑な気持ちを湛えた兄の表情が切ない。その兄が疲れ果てて力尽きようとしたとき、今度は妹が再び兄に魔法をかけようとする。この、小さい子どもたちが抱いている、大きくて尊い愛情が、柔らかく繊細な絵で伝わってくる。表題紙と最後の頁の折り鶴に心が掴まれる。この物語が、国境を、時代を超えた、苦しみと困難に直面している子どもたちの物語であることを教えてくれているようだ。
殺傷能力のある武器を作り、輸出することを推進しようという動きが活発化している。軍事の専門家、と言われるひとたちの口からも「どんどんやったらいい」などという言葉があちこちで聞こえて驚く。平和主義というこれまで一応でも原則とされていたことが、冷笑と蔑みに汚されていく。そのしたり顔の欺瞞を打ち砕くのは、この子どもが抱く悲しみと愛情ではないかと、私は思う。
この絵本は。2021年度 プラチスラバ世界絵本原画展金杯を受賞している。