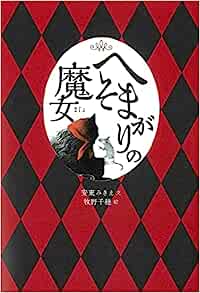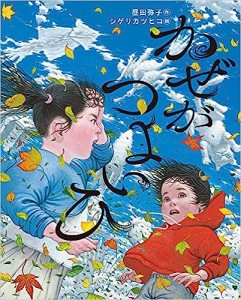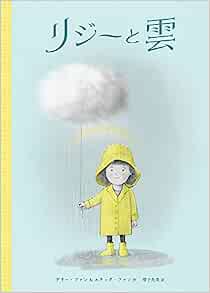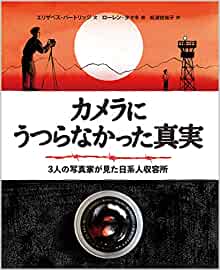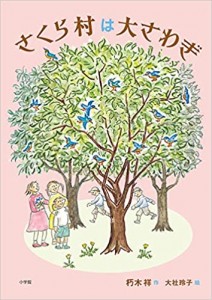元首相が聴衆の目前で銃弾に倒れるというショッキングな事件があった。犯人はカルト宗教信者の家庭に生まれた二世で、その宗教と繋がりのある元首相を狙ったとのこと。同じ宗教ではないが、私も幼い頃から新興宗教にのめり込む母に悩まされてきた。金銭的にも精神的にも、カルト宗教二世は大きなダメージを受ける。いまだに子どもの頃に叩きこまれた価値観が自分のなかに根深く存在することに気づいてうんざりする。人生の基盤をカルトに左右されてしまう子どもの辛さに溜息がでる。だからといって、その恨みを直接的な暴力に結びつけてしまうのは許されることではないのは重々承知しながら、もし彼に自分の苦しみや状況を語る、自分の言葉があったなら、もし自分で綴れないとしても、自分の痛みと響き合い、問題を可視化してくれる言葉や物語に出会っていたら、と思ってしまうのだ。
元首相が聴衆の目前で銃弾に倒れるというショッキングな事件があった。犯人はカルト宗教信者の家庭に生まれた二世で、その宗教と繋がりのある元首相を狙ったとのこと。同じ宗教ではないが、私も幼い頃から新興宗教にのめり込む母に悩まされてきた。金銭的にも精神的にも、カルト宗教二世は大きなダメージを受ける。いまだに子どもの頃に叩きこまれた価値観が自分のなかに根深く存在することに気づいてうんざりする。人生の基盤をカルトに左右されてしまう子どもの辛さに溜息がでる。だからといって、その恨みを直接的な暴力に結びつけてしまうのは許されることではないのは重々承知しながら、もし彼に自分の苦しみや状況を語る、自分の言葉があったなら、もし自分で綴れないとしても、自分の痛みと響き合い、問題を可視化してくれる言葉や物語に出会っていたら、と思ってしまうのだ。
周りがすべて一つの価値観に染まっているなかで自分の言葉を持つことは非常に難しい。抑圧は沈黙を強いるから。しかし、人間が理不尽な力に押しつぶされそうになるとき、人の心を支え、自分のいる場所を客観的に見ることで怒りや絶望を別のエネルギーに変えてくれるのは、「言葉」なのだと私は思う。例えば、隠れ家の日々を批判精神と真摯に思考する言葉で日記に綴ったアンネ・フランクのように。
この『パンに書かれた言葉』という物語は、イタリア人の母と日本人の父を持つ少女、光・S・エレオノーラ(通称エリー)が、東日本大震災をきっかけに、第二次世界大戦下のイタリアでファシズムに抗おうとしたレジスタンス、そしてヒロシマの記憶を旅する物語だ。彼女のミドルネームは最後まで伏せられている。そこに大切な秘密が隠されているから。
物語は東日本大震災の日々から始まる。余震と停電が繰り返されるなか、「毎日のようにテレビに映し出される光景をいやというほど観て、心が痛いのか痛くないのかわからなくなって、しびれたみたいな感じ」になるエリー。戦争に銃による襲撃と、次々と目の前で繰り広げられる恐怖に、同じようなしんどさを抱えている子どもたちは多いのではないだろうか。エリーは両親のすすめで母の故郷であるイタリアのフリウリの村にあるノンナ(祖母)の家にしばらく滞在することになる。そこで、エリーは、ノンナから、ナチスに連れていかれ消息不明になった当時十三歳だった親友のサラと、レジスタンス活動に身を投じたために十七歳で処刑されてしまったノンナの兄、パオロの話を聞くことになる。パオロは、処刑前に一冊のノートと、自分の血である言葉を書き記したパンを残していった。ノンナはずっとそれを大切にしてきたのだ。
世界中に報道されるほどの大震災があった日本からやってきたエリーに、ノンナがナチス支配下の記憶をしっかり話して聞かせるのがとても印象的だ。ノンナはエリーに、素晴らしい家庭料理を作ってくれる。(これがもう、たまらなく美味しそうで涎が出る)その一方で、人間の罪の暗い淵をのぞき込むような過去の記憶を語り、しっかりエリーに伝えようとする。ヨーロッパにおける戦争の記憶の継承のあり方は、特に加害の過去に蓋をしがちな日本とは全く違う。ガス室に送り込まれた人たち、レジスタンス活動で殺されていった人たちの声を、顔と名前を取り戻し、決して忘れない記憶としてすべての子どもたちが継承していくことが大前提なのだ。エリーは、サラとパオロの話をノンナから聞くうちに、これまで、心のどこかで自分と無関係だと思っていたアウシュヴィッツの光景が、まるで今目の前で起こっていることのように思えてくる。どこかの見知らぬ人ではなく、顔と名前のある存在として人間を取り戻す、というのはこういう営みなのだ。
イタリアから帰ってきたエリーは、今度が自分から広島に行き、祖父母が体験した原爆の話を聞き、広島平和記念資料館で、やはり十三歳で被爆し、死んでいった祖父の妹、真美子の写真に出会う。なぜ、真美子は体中を焼かれて死ななければならなかったのか。戦後もピカドンに焼かれた人たちは、差別と後遺症に苦しみ続けた。エリーの祖父母のヒロシマの記憶は、フクシマへ繋がっていく。
チェルノブイリ原発にロシア軍が侵攻し、世界中が震え上がったのは、つい数か月前のことだ。恐ろしかったのは、ロシア軍が、チェルノブイリでも特に放射線量の高いことで有名な森に野営し、兵士たちが被曝したことだ。チェルノブイリの記憶が、全く彼らには共有されていなかった。決して忘れてはならない記憶が、継承されていなかったのだ。ヒロシマもフクシマも、チェルノブイリも、ショア―(ホロコースト)も、決して過去のものではない。現在進行形の、いつわが身にふりかかるかもしれぬ未来でもある。その未来を生むのは、忘却と無関心なのだ。
パオロが処刑前に、自分の血でパンに書き残した言葉が何かは、読んで確かめてほしい。いつまでも、まるでゾンビのように戦争と暴力を繰り返すのを、「人間ってこんなもの」「弱いものがやられるのは仕方ない」などとうそぶいてやり過ごすのは、もういい加減やめにしよう。言葉の力を信じて、素敵なミドルネームを持つエリーとともに何度も記憶をめぐる旅に出よう。美味しいものもたくさん出てくる、愛しい人たちと出会う旅に。大切な人々から聞いたそれぞれの記憶が少女の心のなかで輻輳し、お互いを照らし、響き合いながら、少女の視界を開いていく。共に旅する私たちの心の扉も。だからなのだろうか、辛く悲しい記憶への旅なのに、読後感は優しい光に満ちている。
一冊の本は大切な記憶への扉だ。ただ、羅列的に知識を得るだけなら、ネットでも出来る。しかし、他者の経験や心の動きを通じて歴史の奥行きを体験し、心に刻むことができるのは、厚みを供えた本への旅が必要なのだ。戦争と暴力の恐怖が世界中を駆け巡っている今、この本が刊行された意味はとても大きい。暴力に、同じ暴力で立ち向かおうとする負の連鎖を断ち切るのは、痛みや苦しみへの真の理解と共感を促す言葉の力であることを信じてやまない。