 神は細部に宿るというけれど、この小説における高村さんの仕事の見事さは恐ろしいほどだった。CGなんて目じゃないほどの緻密さで小説が立ち上がってくるのである。圧倒的な力でねじ伏せられ、引きずり込まれる。虚無へ、人間が持つ果てしないブラックホールのような虚無へと連れていかれ、逃れるすべもない。しかし、その中に、ほんの少しだけ見える、人として踏ん張る足がかりがあって、それが合田という、ずっと高村さんと共に歩んできた存在に見え隠れしているのが、今、この時代の『冷血』として高村さんが命がけで提示してくれたものなのかもしれないと思う。
神は細部に宿るというけれど、この小説における高村さんの仕事の見事さは恐ろしいほどだった。CGなんて目じゃないほどの緻密さで小説が立ち上がってくるのである。圧倒的な力でねじ伏せられ、引きずり込まれる。虚無へ、人間が持つ果てしないブラックホールのような虚無へと連れていかれ、逃れるすべもない。しかし、その中に、ほんの少しだけ見える、人として踏ん張る足がかりがあって、それが合田という、ずっと高村さんと共に歩んできた存在に見え隠れしているのが、今、この時代の『冷血』として高村さんが命がけで提示してくれたものなのかもしれないと思う。
この物語の背後にあるのは、フラクタルな、逃げ場のない都会の近郊地の風景だ。著者の高村薫さんが、インタビューで、「16号線があって、初めてこの人物の物語が成立する」とおっしゃっていたが、ここに描かれる16号線の風景は、東京という都会の周り、日本のどこに行っても広がっているような大きな道路沿いに広がる無機質な風景だ。都会と田舎の境目、田舎ほど濃い人間関係もなくて人の出入りも激しいけれど、どこか全てが他人事のような風景だ。トラックとコンビニと、チェーンの飲食店にショッピングモール。車で旅行していると、あまりに同じような風景が続くんで、時々どこを走っているんだかわからなくなることがある。それは、ル=グウィンの言う「同じものが常に、同じものへとつながっていく」「他者はない。逃げ道もない」(※)風景なのかもしれない。その逃げ場のない場所から、二人の殺人者がむっくりと立ち上がり、特に理由もないままに歯科医の一家を惨殺する。高村さんの筆は、その二人の男が身体の中に抱えている、逃げ場のない熱量を文章の細部にまで漲らせる。犯行前の二日間ほどの二人の行動を読んでいると、爆発寸前のような膿が、二人の間に膨れ上がっていくのがわかる。この二人は出会いサイトで知り合った行きずりのような関係性なのだけれど、彼らにはある共通性があると思う。それは、思考停止だ。
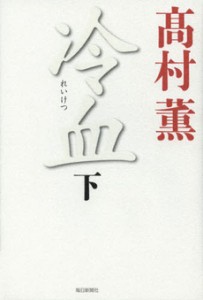 犯人の二人は、一家四人を即死させるような理不尽な犯罪のあと、まことに幼稚な行動をとる。何だかもう、犯罪を隠すのもめんどくさい、というような投げやりさなのだ。ペタペタとあちこちに足跡をつけた二人は逮捕され、そこから合田も含めた捜査班の徹底的な検証が始まる。生い立ちから成育歴、当日の行動から何もかも調べ上げられ、追求されるのだけれど、そこには犯罪に繋がる「なぜ」という理由はまったく見当たらない。ただただ、二人のたどった、やり切れない人生の風景だけが延々と立ち上がるだけなのだ。その一つ一つは犯罪と明確な繋がりは持たないのだけれど、少しずつ積み重なることで、親不知が腐る圧倒的な疼痛のように彼らから思考能力を奪い、雪崩が起きるように理不尽な暴力へと二人を押し流していく。「考えていたら、やってません」という彼らの言葉は、掛け値なしに本当なのだ。私には、その思考停止が、「冷血」というテーマに繋がるものだと思えて仕方なかった。そして、彼らのような思考停止は、私の中にも巣食うものであると思わざるを得ないのだ。
犯人の二人は、一家四人を即死させるような理不尽な犯罪のあと、まことに幼稚な行動をとる。何だかもう、犯罪を隠すのもめんどくさい、というような投げやりさなのだ。ペタペタとあちこちに足跡をつけた二人は逮捕され、そこから合田も含めた捜査班の徹底的な検証が始まる。生い立ちから成育歴、当日の行動から何もかも調べ上げられ、追求されるのだけれど、そこには犯罪に繋がる「なぜ」という理由はまったく見当たらない。ただただ、二人のたどった、やり切れない人生の風景だけが延々と立ち上がるだけなのだ。その一つ一つは犯罪と明確な繋がりは持たないのだけれど、少しずつ積み重なることで、親不知が腐る圧倒的な疼痛のように彼らから思考能力を奪い、雪崩が起きるように理不尽な暴力へと二人を押し流していく。「考えていたら、やってません」という彼らの言葉は、掛け値なしに本当なのだ。私には、その思考停止が、「冷血」というテーマに繋がるものだと思えて仕方なかった。そして、彼らのような思考停止は、私の中にも巣食うものであると思わざるを得ないのだ。
私の人生にも、彼らのように積み重なってどうしようもない風景がある。犯罪は侵さないけれど、そこから目をそらして考えないようにすることで、成り立っている日常があるのは事実だし、自分の人生から目をあげても、やはりそこには累々と積み重なっているやり切れない風景が広がっている。私は最近になって漸く戦争や、ヒロシマと長崎の原爆投下や、貧困や、原発について考えるようになった。それらについて少しずつ勉強し始めて思うことは、これまでの自分の徹底的な無関心と思考停止だ。こんな大きなことを自分のような小さな存在が考えてみたところで、なんになるだろう。それよりは、自分の目に見えていることだけを考えて過ごしたほうが、精神衛生にもいいし、という感覚でほったらかしてきたことがたくさんある。その自分の無関心を振り返ってあれこれ考えていると、私と同じような無関心の洞が、あちこちに空いているのが見えるような気がする。私もやっとその洞を見始めたところなので、何の偉そうなことも言えないし、その洞を見つめれば見つめるほど、どうしようもない人間存在のカオスにはまり込んでいくことは目に見えているのだけれど、その洞に目を凝らしておかないと、大変なことになるんじゃないか(いや、もう、なっているんだと思うけれど)という予感がしているのだ。『新潮』の2月号「有限性の方へ」という評論の中で、加藤典洋さんが、今私たちの足元に空いている巨大な穴ぼこについて言及されているけれど、たとえ視界に入らないような大きすぎる穴ぼこであっても、「仕方ない」という思考停止だけはしてはいけないように思う。この年齢で青臭いといわれても、マイノリティとして小さな小さな声に過ぎなくても、考えて、それを言葉にしていかなければ、この穴ぼこはもっと巨大になってしまうような気がする。この『冷血』という物語の男たちに穿たれている思考停止という洞は、今、私たちの中に、足元に空いている穴ぼことそういう意味で繋がっていると思うのだ。
その巨大な穴ぼこの前で、ただひたすら目をそらさずに見つめる役割をはたしているのが、合田という人間だ。この『冷血』というブラックホールのような暗闇の中で、唯一光となって掲げられるのは、この犯罪と二人の男に正面から向き合い、ひたすら泥臭く正体の見えない暗黒を見据え続けた合田という男の眼差しだと思う。犯人にも「学生のようだ」と言われるような合田は、輪郭を持たない化け物のような彼らの犯罪を調べつくし、何とかして言葉にしようとあがき続ける。この物語のほとんどは、その営みで埋め尽くされている。そして、世間が彼らのことを忘れる頃になっても、彼らにハガキを書き、会いにいく。何度わからないと言われても、とにかく彼らの言葉を聞き、彼らと同じ映画を見たり本を差し入れたりして読んだ感想を述べ合ったりする。そんな高村薫さんがおっしゃるように、「事件を超えて人間そのものと向き合うようになった」合田に対し、殺人者である井上が書き送るハガキの内容が、「文学」なのだ。多分彼らにも、自分自身の犯したことは「わからない」ことなのだと思う。でも、合田との、まるで合同作業のような検証と、「人間として」彼らと向き合う眼差しから、井上の中に言葉が生まれてくる。その言葉は、生きて思いを伝え合うからこそ生まれる、『冷血』の中に微かにめぐる希望なのかもしれないと思う。希望という言葉を使っていいかどうかわからないほどの希望ではあるけれど。そのほのかな温かみは、冒頭に置かれている、もう誰とも思いをかわすことの出来ない殺されてしまった少女の日記の言葉が放つ死者の孤独を際立たせる。彼女の日記は、誰も受け止めてくれる人がいないまま、打ち捨てられるのだ。血のつながった祖母にさえも、「見たくもない」と言われてしまう、少女が唯一残した言葉たちが不憫で仕方なかった。それに比べて、井上には最後の最後まで自分の言葉を聞いてくれた合田がいた。少女と井上を分けていたのは、生きているかどうかという違い、その言葉を受け止めてくれる誰かがいるかどうかの違いなのだ。その理不尽も含めて、「生きよ」とぎりぎりの場所から発する高村さんの問いかけは、カポーティの『冷血』をそのまま使ったタイトルに相応しい、今読むべき本だと思う。図書館の返却期限があったので、だいぶ急いで読み飛ばしてしまった。これは、買ってじっくり読み直さなければな、と思う。
(※『いまファンタジーにできること アーシュラ・K・ル=グウィン 河出書房新社)
2012年12月刊行
毎日新聞社
