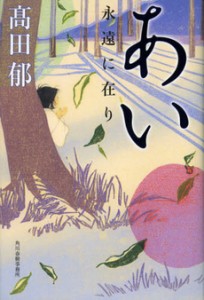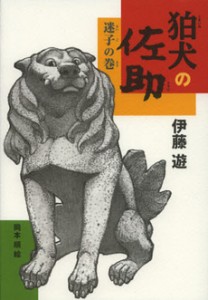「佇まい」という言葉が好きだ。存在自体が醸し出す気配。そこに在る、ということが美しさにつながるような。多分それは、長い時間をかけて積み重ねてきたものが醸し出すもの、しかも何か一つのことに心をこめて生きてきた人のみが身につけるもの、という気がする。この本は、山王書房という古本屋さんを営んでいた関口良雄さんが、文人たちやお店の客人たちの想い出を綴ったもの。一度もおじゃましたことのない山王書房の古本の匂いのするような、とても心惹かれる佇まいの本なのだ。きっと、山王書房も、この本のように、ふと気が付いたらそこに何時間もいてしまうような、魅力ある古本屋さんだったに違いない。ああ、行きたかったなあ。私はビビリだから、きっとゆっくりお話などは出来なかっただろうけれども、関口さんが愛した本の数々を、じっくりと拝見したかった。本に対する愛情が、いっぱいに詰まったこの本を読んで、しみじみとそう思った。
「佇まい」という言葉が好きだ。存在自体が醸し出す気配。そこに在る、ということが美しさにつながるような。多分それは、長い時間をかけて積み重ねてきたものが醸し出すもの、しかも何か一つのことに心をこめて生きてきた人のみが身につけるもの、という気がする。この本は、山王書房という古本屋さんを営んでいた関口良雄さんが、文人たちやお店の客人たちの想い出を綴ったもの。一度もおじゃましたことのない山王書房の古本の匂いのするような、とても心惹かれる佇まいの本なのだ。きっと、山王書房も、この本のように、ふと気が付いたらそこに何時間もいてしまうような、魅力ある古本屋さんだったに違いない。ああ、行きたかったなあ。私はビビリだから、きっとゆっくりお話などは出来なかっただろうけれども、関口さんが愛した本の数々を、じっくりと拝見したかった。本に対する愛情が、いっぱいに詰まったこの本を読んで、しみじみとそう思った。
「古本屋という職業は、一冊の本に込められた作家、詩人の魂を扱う仕事なんだって。ですから私が敬愛する作家の本達は、たとえ何年も売れなかろうが、棚にいつまでも置いておきたいと思うんですよ」
後書きの息子さんの言によると、関口さんはいつもこうおっしゃっていたとか。そんな風に関口さんに愛されて誰かのもとに旅立っていった本は、なんて幸せなんだろうと思う。きっとお店には、そんな関口さんの想いがいっぱいに詰まっていただろうから、お客さんもきっと本を愛していた人がほとんどだっただろう。そんな風に本を愛する人、というのは概してあまりお金儲けが得意でない。というか、本ばかり読んでいるので、お金儲けをする暇もない(笑)この本に出てくる昔日のお客さんたちも、そんな人ばっかりだ。書斎を作って、そこで本ばかり読んでいる植字工さん。部屋に本と美術書しかなかった井上さん。そんな方たちのお話を読んでいると、何だか私は安心してしまうのだ。本を愛して、本に淫して一生を過ごしていった人たちと、この本を通じてなんだか繋がっているような気がするのである。世の中からはあまり理解されないかもしれない、本好きたち。もう、この本に出てくる方たちも、関口さんも、とうに御存命ではないけれども、きっと彼らはあの世でも、本の話ばかりして笑っておられるような気がする。そう、「二人の尾崎先生」という項での、尾崎一雄氏宅での夜のエピソードのように。書庫で語り明かし、「あなたがたは、いつまで話しているんですか」と夫人に言われ、手料理を頂きながら、また本の話。本を買いに行ったことも忘れて、本を包むはずの風呂敷に蜜柑をいっぱい包んで帰る夜。これを、至福と言わずになんと言おうか。私も、あの世にいったら、ぜひ関口さんのお仲間に、本好き山脈の一端に加えて頂きたいと、思うのである。…それまでに、ちゃんと勉強しておかなきゃ。そう言えば、この本はやっぱり本好き山脈仲間のぱせりさんのブログで教えて貰ったのだ。私たちはネットのおかげで近くにはいなくても、こうして繋がっていられる。本好きは、本好きを呼ぶというのは昔から変わらない。その感謝も感じる一冊だった。
関口さんの敬愛された上林暁氏の本を、去年一冊買ったまままだ読めていなかったのを思い出した。昔日にならぬうちに、早く読まねば・・・。
2010年10月刊行
夏葉社