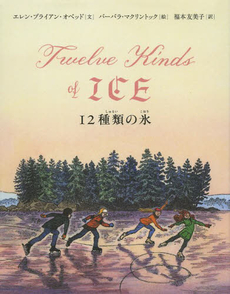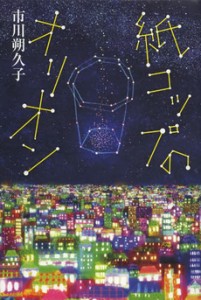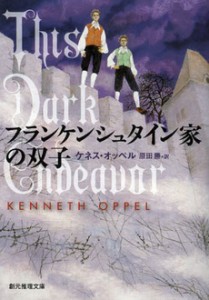子ども向けに、図書館をどう使うか、どう図書館と仲良くなるかを書いた本なのだけれど、これがとってもわかりやすくて、伝えるべきことをしっかり踏まえている内容になっています。図書館で働いてる私でさえもなるほど~、と思うくらいです。大人の方が読んでも、きっと目からウロコのところがあるはず。
子ども向けに、図書館をどう使うか、どう図書館と仲良くなるかを書いた本なのだけれど、これがとってもわかりやすくて、伝えるべきことをしっかり踏まえている内容になっています。図書館で働いてる私でさえもなるほど~、と思うくらいです。大人の方が読んでも、きっと目からウロコのところがあるはず。
この本には、図書館で出来ることがたくさん書いてあります。本を読む、借りる、本で調べる。もちろんそれが基本なのですが、私が一番いいな、と思ったのは「図書館では、なにかをしなければいけない、ということは1つもないのです。こんな自由な場所は、ほかにそうそうありません」という言葉。そう、その通りなんですよねえ。本はたくさんあるけれど、別に読まなくたってかまわない。反対に、どれだけ読んでもかまわない。誰にもなんにも強制されません。この本にも書かれていますが、様々なジャンルの本を、なるべく偏りのないように収集する。この本が読みたいとリクエストされれば、その希望を叶えるべくあちこちに問い合わせて提供します。そう、図書館は「自由」が基本なのです。そのために、図書館は資料収集の自由と、提供の自由を宣言しているんです。(「図書館の自由に関する宣言」を、リンクしておきます。私は時々、この宣言を読むことにしています。何かこうね、ぎゅっと身が引き締まる思いがします。 )その自由を、最大限に活用して貰いたいなあと思うんですよ。なぜなら、この自由は活用して、使い倒すことで、もっと活性化して広がっていくと思うから。
だいたいの図書館は地方自治体が運営している「市民の図書館」なのですが、こんな風に公共図書館が出来るまでには、先人たちの努力と闘いがあったのです。それこそ女性や子どもに貸し出しをするようになったのも、そんなに昔のことではありません。はじめから当然のようにあるものではないからこそ、どんどん使って、実績を作って、この社会になくてはならぬものとして根付いて欲しいのです。日本では、そこがまだまだだと思うんですよねえ。「これだけネットがあるんだから、何も本でなくても」という声もあるでしょうが、やはり一冊の本が持つ情報量の多さと確かさは、ネットで検索して見る頁とは格段に違います。客観性も違います。この本にも「なぜ本でさがすかというと、たいていの本は専門家が書いていますし、出版される前に何人もの人が、正しいかどうかを確認しているからです」とあるように、ネットで個人的に書いているものと、出版されるものとはその責任の取り方が根本的に違います。ネットは匿名が基本ですもんね。
そして、図書館のいいところは、同じテーマの本が何種類も揃っていること。調べたことを鵜呑みにしないで、別の角度からも見ることができる。この本には、そこもちゃんと書いてあります。「1冊見て終わりではなく、2冊以上の本を使って確認しよう」その通り。活字で書かれているからと言ってそれを鵜呑みにしない、というのも大切なことです。いろいろ調べて同じテーマで違うことが書いてあったら、それは自分で考えてみる余地があるビッグチャンスですもんね!それだけで自由研究ができちゃう。卒論もできちゃうかもしれない。「なぜだろう」と思って自分で調べて、自分の頭で考えて「これだ!」という解答を手に入れることって、ほんとに楽しい。解答を得られなくても、これまたずっと考え続けるという楽しみが生まれます。また、答えは一つでなくてもいいかもしれない。答えは無いのかもしれない。でも、なぜだろうと思って考えることが、人間に与えられた一番の楽しみであると私は思います。そして、もちろん、何にも考えないために図書館に来るのも、いいですよねえ。いろんなことに疲れて、家や学校から離れたいとき。一人でいるのも寂しいけれど、誰とも話したくないとき。人間関係に疲れて、生きていくのがめんどくさいよな、と思うとき。図書館にきて、ぼーっとして、綺麗な写真集や、美しい絵画を眺めたり。漫画を読んでみたり。居眠りしたりするだけでも、ほっと出来るかもしれない。誰に気を遣う必要もないのが、また、図書館のいいところです。安心してひとりになれる。そして、本ほどひとりになった人間の味方をしてくれるものはありません。
「学校は何年かたつと卒業しなければなりませんが、図書館に卒業はありません。何歳になっても行けます。もし図書館があなたのお気に入りの場所になったら、一生ずっと遣い続けることができますよ」
いいこと言うなあ。私もきっと一生図書館には通い続けるでしょうねえ。他にもいっぱいしびれる名言がたくさんあって、この本付箋だらけになってしまいました。「私は図書館のことよく知ってるから」と思う方にもおすすめです。そうそう~~!と嬉しくなって、明日図書館に行きたくなること、請け合いです。
2013年10月刊行
講談社