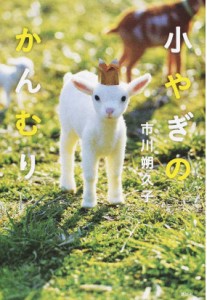スラブ叙事詩を見てきた。予想を遙かに超えて巨大だ。展示できる場所を選ぶこの巨大さは、なぜ必要だったのだろうと思っていたのだが、実物を見て納得するところがあった。これは体験型の絵画なのだ。ミュシャはサラ・ベルナールという大女優の舞台装置や衣装、ポスターを作り上げていた。今で言うプロデューサーのような役割をしていた人だ。その経験も踏まえ、空間が持つ力を最大限に引き出すことで、自分の描く歴史の一瞬を、見るものに肌で感じて欲しかったのではないだろうか。
スラブ叙事詩を見てきた。予想を遙かに超えて巨大だ。展示できる場所を選ぶこの巨大さは、なぜ必要だったのだろうと思っていたのだが、実物を見て納得するところがあった。これは体験型の絵画なのだ。ミュシャはサラ・ベルナールという大女優の舞台装置や衣装、ポスターを作り上げていた。今で言うプロデューサーのような役割をしていた人だ。その経験も踏まえ、空間が持つ力を最大限に引き出すことで、自分の描く歴史の一瞬を、見るものに肌で感じて欲しかったのではないだろうか。
例えば『原故郷のスラブ民族』の、星空に浮かぶ異教の祭司から見下ろされる威圧感。そして、何より見るものと対峙し、こちらをみつめる二人の男女の凍り付くような眼差しは、強烈だ。今、まさに背後から襲いかかりつつある、殺戮者たちの息づかいや激しい足音の気配が、この眼差しに凝縮している。そして、この眼差しは、この一枚だけではない。どの絵にも、明らかに「見る者」を意識した眼差しでこちらを見つめてくる人物がいる。あなたは今、目撃者になった。見てしまった以上、この出来事と無関係ではいられないのだよ、という眼差しだ。戦いで殺されてしまった人々、故郷を追われさまよう母と子どもたち。ミュシャが描いているのはスラブ民族の人々の歴史だが、民族や宗教の対立をきっかけにした憎しみは、今も世界中に渦巻いている。画布の向こうから見つめ返す眼差しに、こんなに射貫かれてしまったのは、私自身、迫り来る暴力の足音に大きな不安を抱えているからなのだろうと思う。
また、画面はどんなに巨大になっても、そこに存在する人たちは、一人一人の確かな体温と自分だけの顔を持って描きあげられている。『ニコラ・シュビッチ・ズリンスキーによるシゲットの対トルコ防衛』では、戦いのさなか、火のついた松明が火薬に投げ込まれる、その瞬間が描かれている。画面いっぱいにひしめく、人、人、人。梯子によじ登ろうとしている人も、疲れて座り込んでいる人も、何かを囁き合う人たちも、次の瞬間には全てこの爆発に巻き込まれてしまうのだ。画面中央の黒い帯がそれを暗示して不気味に流れている。私はこの黒い帯に、原爆投下のきのこ雲を連想した。その瞬間まで、自分の運命を知らずに生きていた人たちの顔がここには刻みつけられている。
「見る」ことは、どうしても見るものと見られるものを分かつ。この戦闘を絵にし、客観化してしまうことは、古典絵画の戦闘シーンのような「ただ眺めるもの」として片付けられる危険性も生んでしまう。今の3D技術がある時代なら、ヴァーチャルで体験させてみたいと思うところかもしれないが、ミュシャは、暗黒を絵の中央に出現させることで、この一瞬後を想像させる推進力を絵に込めたのだ。この推進力はヴァーチャルな世界よりも強いメッセージを生むのだと私は思う。ここに刻みつけられた「瞬間」には終わりがない。だからこそ、永遠の問いかけとして見るものの心に刻印されるのだ。芸術が生み出す力を強く感じた一日だった。