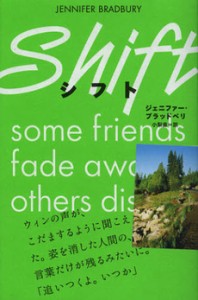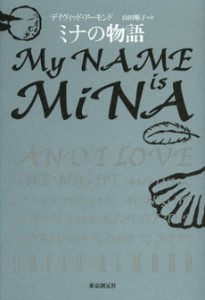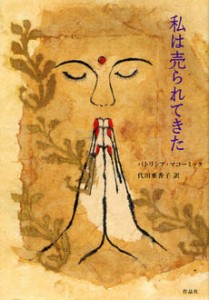前作の『ブリジンガー』から3年あまり。待っていた完結編が刊行されました。上下巻の力作です。ただ人がたくさん死ぬ戦闘ファンタジーは苦手なんですが、この物語は単なる善悪の二元論に止まらず、争いという出来事の中にある人間の複雑さや心情をしっかり描き出しています。手に汗握る展開といい、キャラクターの魅力といい、この分厚さを一気に読ませて圧巻です。
前作の『ブリジンガー』から3年あまり。待っていた完結編が刊行されました。上下巻の力作です。ただ人がたくさん死ぬ戦闘ファンタジーは苦手なんですが、この物語は単なる善悪の二元論に止まらず、争いという出来事の中にある人間の複雑さや心情をしっかり描き出しています。手に汗握る展開といい、キャラクターの魅力といい、この分厚さを一気に読ませて圧巻です。
そう、この物語の読みどころは、戦争という特殊な状況の中での、主人公たちの内面の葛藤や弱さが克明に描かれるところだと思います。ドラゴンライダーとして、ガルバトリックスという最強の敵と対峙しなければならない重圧に苦しむエラゴン。寄せ集めの軍隊をまとめて指揮をとるナスアダは強い女性ですが、今回は敵に誘拐され拷問を受けるという苦難に陥ります。そして、魔力も特別な能力も持たずに、自らの知恵と力だけで妻子を守り抜こうと苦闘するローラン。命をかけたぎりぎりの場所でまっすぐ自分の弱さを見つめた時に、もう尽きたと思った場所から新しい力が溢れてくる。そこに大きなドラマがありました。
でもねえ、ほんとにたくさん人が死ぬんですよ。息子たちがやっている「三国無双」を連想するくらい。ちょっとうんざりしかけました。でも、読んでいるうちに、そのあたりの矛盾も、作者は意識して書いてるんじゃないかと思ったんです。敵はばったばったとなぎ倒して死に対する感覚も麻痺するぐらいなのに、自分の身内の死に対しては深い喪失感に苦しむ。戦争の中で、エラゴンの身内に赤ん坊が生まれます。口に障がいを持って生まれたその子を、エラゴンは時間と力を使って必死に治すんです。何百人という人を殺したその手で。でも、本当はなぎ倒される名も無い兵士(実は名も無い兵士なんていないのですが)一人一人に家族があり、大切な人生がある。そこを感覚的に切り捨てる無自覚の怖さと、無自覚に気付いたときの苦しみ。その矛盾と葛藤の中に人は生きている。
それを象徴するのが、エラゴンとガルバトリックスとの最後の戦いと戦後処理の描かれ方です。ネタバレになってしまうので、あまり詳しいことは書きませんが、最後の戦いでは、相手を力でねじ伏せるのではなく、「理解」を求めるところから活路が見いだされる。この迫力溢れるシーンは圧巻でしたが、その戦いで勝利を収め(そこは予定調和だから書いていいよね)英雄になったエラゴンの身の処し方に、ああ、そうなのか、と私はこの物語のテーマが腑に落ちるような気がしたんです。ここも書いてしまうとこれから読む人が面白くないんで、明言は避けますが。エラゴンは、ガルバトリックスが犯した過ちを二度と繰り返さぬために、栄光とは無縁の、厳しい生き方を選ぶのです。そこには、ル=グウインの言うヒロイックファンタジーの本質ー「人が過ちを犯すこと。そして、ほかの人であれ、本人であれ、誰かがその過ちを防いだり、正したりしようと努めて、けれどもその過程で、さらに過ちを犯さずにはいられないこと」を描き出そうとする営みがありました。これを読んだ子どもたちは、ハラハラドキドキしながら、自分自身と語り合い、矛盾も含めた人間という存在に思いを馳せることになると思います。この壮大なファンタジーを締め括りに相応しい爽かなラストも良かった。何はともあれ、最後までこの分厚さにめげずに読み終われてほんとに良かった(笑)
2012年11月刊行 静山社
※表紙の画像を入れたいのですがiPadでどうしたらそれができるのかわからない。ああ。。。普通のパソコン欲しい(笑)