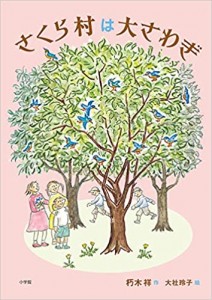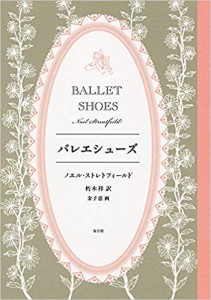家の近くを飛び交う鳥たちを見ながら、数メートル、時に数千メートルの高度まで飛べる鳥たちには、私たちと全く違う世界が見えているのだろうといつも思う。
家の近くを飛び交う鳥たちを見ながら、数メートル、時に数千メートルの高度まで飛べる鳥たちには、私たちと全く違う世界が見えているのだろうといつも思う。
うちの猫たちも、少し開けた窓から外の空気を嗅ぐとき、この町内に住んでいるもの、通り過ぎていくものの気配を、アンテナをびんびん立てて感じている顔をしている。
当たり前だけれども、猫は人間とは違う種族なので、同じ空間にいても、私たちには見えない異世界への扉を持っている。それでいて、寂しがり屋だったり、甘えん坊だったり、やきもちを焼いたり、いたずらして隠れてみたり、一緒に暮らしていると、感情や心のありようが、驚くほど人間と変わらない。
この物語には、そんな猫の魅力がいっぱいに詰まっている。三匹の猫と暮らす私の心のツボにすっぽりはまってくる素敵な物語だ。
主人公の小学生の信ちゃんが愛犬のダンと公園で散歩していると、一匹の茶トラの子猫がダンの足元に走り込んできた。思わずかぶっていた野球帽に入れて連れて帰った、かぼちゃプリンのような色のトラノスケは、大きなダンもタジタジの元気な子。
余談だが、朽木さんの物語に登場する、優しくて食いしん坊のダンが、ほんとに好きだ。彼は、犬種族の信頼と愛情を体現するような存在だなあといつも思う。信ちゃんと、心配性のお父さん、動物大好きのお母さんに可愛がられて、トラノスケは家族の一員になっていく。大きくなった彼は、「ねこのごようじ」のためにお出かけするようになる。トラノスケがどこに行くのか気になる信ちゃんは、こっそりあとをついていき、「ねこのごようじ」の秘密をさぐってみるのだった。
うちにも、トラノスケとそっくりの茶トラくん(現在16歳)がいて、その昔、わが家の周りが田んぼだらけの頃はお外で遊んだりしていたのだ。でも、あっという間に田んぼが埋め立てられ、車の通りも多くなって、心配性の私は、信ちゃんのお父さんのように、彼が帰ってくるまで胃に穴があくほど心配で心配でいてもたってもいられず、ここ十年以上、室内飼いを貫いている。でも、今も思い出す。遊び疲れて、満ち足りて眠っていた寝息。お外に出るとき、意気揚々と弾んでいた足取り。カエルを咥えて帰ってきて大騒ぎしたこと。そして、トラノスケの親友のコタロウと同じように、仲良しのハチワレがいて、いつも一緒に遊んでいたこと。一日遊んで帰ってきたうちの子から、なんともいえないお日様の匂いがしていたこと。あれは、平和の幸せな匂いだ。
遊んで、可愛がられて、おなか一杯食べて、コテンと寝こけて。この物語には、そんな、猫と子どもの幸せがいっぱいに詰まっている。猫と人間、犬と猫、犬と人間。お互い持ってる時間軸も種族も違うけれど、お互いの聞こえない声に耳をすませて、愉快に、共に生きることが出来る。出来るんだよ、という声が聞こえて、ここ最近の、恐ろしい出来事に冷え切った心と指先をふんわり温めてくれる。この物語のトラノスケと信ちゃんは、光村図書の三年生の国語教科書に掲載された「もうすぐ雨に」にも登場するふたり。朽木さんの物語は、先行作品の世界と重なりながら、波紋のように広がり、深まっていくのが、読んでいてとても嬉しく、楽しい。物語と友だちになることは、自分の座る椅子がそこに出来る、ということだ。高橋和枝さんの可愛い絵は、トラノスケと信ちゃんがいる、暖かい陽だまりの居場所に読み手を連れていってくれる。特に、裏表紙のトラノスケのお尻がお気に入り。猫がお尻を見せてくれるのは、友情の証。こっちにおいで、と誘ってくれている。子どもの持つ、小さきものへの優しい眼差しが、トラノスケの心の声となって響いてくる、子どもと共に大人にも読んでほしい作品だ。