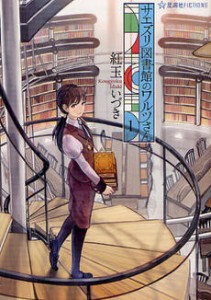 最初は、ごく普通の町にある図書館の物語かと思っていました。しかし、どうも違うらしいと気づいてから一気に面白くなって読みふけることに。この物語は、近未来の図書館。しかも、本というものがとてつもなく高価で手に入りづらくなってしまった時代の図書館のお話です。まるで骨董品のような扱いを受けている紙の本。それを、登録さえすればただで貸してくれるという、この時代には非常識な場所。それがサエズリ図書館です。そこには、ワルツさんという若くて聡明な特別探索司書(!)がいて、「こんな本が読みたい」というと魔法のように本を揃えてくれる。自分のような本読みが、もしこんな時代に放り込まれたら・・と思うと、えらく切なくなってしまうシチュエーションです。文章も、どことなく切なさを湛えていい感じ。
最初は、ごく普通の町にある図書館の物語かと思っていました。しかし、どうも違うらしいと気づいてから一気に面白くなって読みふけることに。この物語は、近未来の図書館。しかも、本というものがとてつもなく高価で手に入りづらくなってしまった時代の図書館のお話です。まるで骨董品のような扱いを受けている紙の本。それを、登録さえすればただで貸してくれるという、この時代には非常識な場所。それがサエズリ図書館です。そこには、ワルツさんという若くて聡明な特別探索司書(!)がいて、「こんな本が読みたい」というと魔法のように本を揃えてくれる。自分のような本読みが、もしこんな時代に放り込まれたら・・と思うと、えらく切なくなってしまうシチュエーションです。文章も、どことなく切なさを湛えていい感じ。
どうやら、大きな戦争があり、その前と後とで大きく全てが変わってしまっているらしい。そして、このサエズリ図書館が出来た経緯も、ワルツさんがたった一人でこの図書館の全書物を所有していることにも、複雑で悲しい事情が絡んでいるらしい。らしい・・というのは、まだこの物語は「1」で、全てが語りつくされているわけではないからです。一篇ごとに秘密を小出しにする感じが、また後を引いていくのだけれども・・・全ての情報が「端末」で所有されるという設定の中で、「紙の本」が人に働きかけるものが、一層心に沁みました。手の中の重み。紙の匂い。新しい本を一度読むと、少し自分の痕跡が残ること。持ち主がいなくなっても、変わっても、大切に保管されていれば本は長い時間を生きます。一冊の本には命があって、持ち主と一緒に時間をその体に刻んでいく。目の前からいなくなった人とだって、本を開いて同じ世界に飛べば、想いを共有することが出来る。そんな紙の本にしかない温もりが、ワルツさんの本を愛する気持ちとともに伝わってくるようでした。
印象的だったのは「第四夜」の中のワルツさんのひとこと。サエズリ図書館の本を持ちだした女性の「一冊ぐらい、一冊ぐらいいいじゃないですか!」という言葉に対してワルツさんが言います。
「かって、この地で、人はいっぱい、亡くなりましたね」 「たくさん亡くなったんだから、ひとりひとりのことなんて、どうでもいいって。ひとりぐらい死んだっていいって、そう思いますか?」
数の多寡というものに、何故か人は左右されます。殺人なら糾弾されるのに、遥かに多い命が失われる戦争ではそうではないし。数が少ないパンダは何億ものお金で取引されて、たくさん生まれてくる猫や犬は、何十万匹も殺処分して平気だったり。図書館の本が受けることが多い受難も、本屋さんが悩む万引きというやつも、そんな危うさと繋がることなのかもしれません。そして、もしかしたら、そんな危うさは、この物語の中で、終末戦争のボタンを押してしまう過ちにも繋がるものなんじゃないか。自分が愛する本だから、私はこの物語に痛みを感じる。でも、こんなふうに数という目に見えるものに騙されて、見過ごしてしまっていることが私にもあるんだろうなと、考えてしまいました。
あと、このワルツさんが、「特別探索司書」という設定が凄い!何が凄いかというと、ワルツさんは、本に内蔵されたマイクロチップから図書の位置情報にアクセスする権限があるらしい。つまり、どの本がどこにあるか、ということを離れた場所から探索することが出来るらしいのです。これはもう、よだれが出るほど羨ましい(笑)本は、油断するとすぐに迷子になります。何十万冊という本の迷路に隠れてしまう。そんな迷子を捜すのは、私のお仕事の一つです。私はこれが何故か人より得意で、いつのまに~か、私だけのお仕事になってしまったという・・・。常に図書館の中を歩きまわって、棚の本を一冊一冊食い入るようにみつめ、いなくなってしまった子(本)を探しております。いなくなった本を呼ぶと、「は~い」「ここ、ここ」と答えてくれるような超能力が欲しい・・・と思いますね、ほんとに(笑)もちろん、図書館には守秘義務があるので、ワルツさんのような権限を持つというのはとても難しいことなんですが。紅玉さんは、後書きを読むと、どうやら図書館のお仕事をされていた様子。きっと、同じ願望をお持ちだったのだと親近感がわきました。
この後の展開がとっても気になるので、楽しみに2巻を待っていようと思います。
2012年8月刊行 星海社
カテゴリーアーカイブ: YA
私は売られてきた パトリシア・マコーミック 代田亜香子訳 作品社
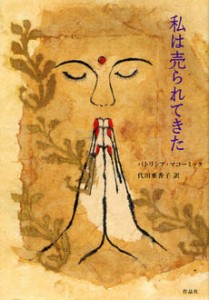 これは、非常に辛い本です。
これは、非常に辛い本です。
毎年、たくさんの・・後書きによると、年間一万二千人近いネパールの少女たちが、インドの売春宿に売られているとのこと。それも、たった300ドル。円高であることを考慮に入れても、たった三万円くらいのお金と引き換えに、売られていく。この本は、その少女たちのことを実際に取材し、自分の目と足で確かめた著者が、一人の少女を主人公に、物語という形にまとめたもの。ですので、フィクションですが、この本に書かれていることは、事実です。今も、この世界のどこかで起こっていること。読めば読むほどに辛いです。でも、目をそらしてはいけない現実でもあります。
主人公のラクシュミーは、ネパールの山の村で生まれた女の子。荘厳な山の自然の中で、彼女は母と、義父と、兄弟たちと暮らしている。彼女が初潮を迎えた頃、村は洪水に見舞われ、働かない義父のせいもあって彼女の家は貧窮する。もともとラクシュミーに辛くあたっていた義父は、ほんのわずかなお金を引き換えに、彼女を売ってしまう。自分がどこに行くのか、何をさせられるのか、知らないままに遠くに運ばれてしまったラクシュミー。彼女を、過酷な現実が待っています。その一部始終が、押さえた筆致で、冷静に描かれています。ラクシュミーが、母を、兄弟たちをどんなに愛していたか。故郷の山々を、どんなに切なく思い出すことか・・。その思い出を散々に汚してしまうような、悲惨な出来事が、どれだけ彼女の心を、身体を引き裂くことか。私たちは、21世紀になっても、この貧困ゆえに女の子が売り飛ばされることさえ終わらせることが出来ない。その事にうなだれます。
こういう悲劇を食い止めるために、行わなければいけないことは、たくさんあると思うのだけれど、まずは教育なんだろうと思うんですよ。文字を知る。本を読む。様々な価値観があることを知る。自分の身体を大切にする権利を、誰かが奪うことが間違いだという事。例え、それが親であっても。人間を売り買いしてはいけない事。男も女も、性によって暴力を受けてはいけない事。私たちはその事を当たり前だと今は思っているけれど、つい戦前までは日本にも、この本に書かれているような現実があった。それは、そんなに昔のことではないんだから・・・。
後書きで、著者が、このような悲惨な状況から逃れた少女たちに実際に会ったことが書かれています。自分たちの置かれていた現実の問題に気づき、様々な活動をしている少女たちは、人間としての誇りと尊厳をかけて、自分たちのような少女たちが少しでも減るように頑張っているらしい。その尊厳を取り戻すのも、また知識の、教育の力だと思う。人として生まれたものが、等しくきちんとした教育が受けられる。そんな最低限のことが出来る世の中に・・なって欲しいと、まるで人ごとのように書く自分が嫌になってしまうけれど。同じ女として、この本を読んでいる間中、心と体が痛かった。
著者もきっと非常に辛い想いをした事だと思いますが、感情に流されず、悲惨な体験をした少女たちの尊厳を、きちんと尊ぶ姿勢でこの本を書いている。その事が伝わってくる文章でした。
あたしの名前はラクシュミーです。
ネパールから来ました。
わたしは十四才です。
この結びの文章がいつまでも胸に残ります。身体の中に鈍痛のように・・・。
2010年6月刊行
作品社
by ERI
クラバート オトフリート・プロイスラー 中村浩三訳 偕成
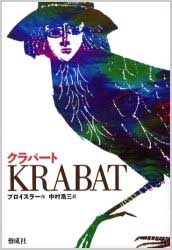 土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。
土と因習の匂い。死が背中あわせに待つ閉塞感。これは児童書でありながら、人の無意識の中に巣くう 夢魔が形をとってあらわれたような物語です。舞台は近世ドイツの、湿地帯にある水車小屋。
村をまわって物乞いをする貧しい生活にくたびれた14才の少年、クラバートはある日夢で彼をさそうカラスの夢を見る。その声にしたがってコーゼル湿地のほとりにある水車小屋にやってきた彼は、まるで当たり前のようにそこで働くことになる。なにしろ寝るところと食べるものがある、というだけでもクラバートにとってはありがたいことなのだ。しかし、そこはただの水車小屋ではない。親方は魔法使いで、どうやら十一人の職人は彼に魔法で縛られているらしい。それが証拠に、単調な労働に嫌気がさして逃げようとしてもどうしてもそこからは逃げられない。そして辛い見習いの期間が終わると、昼間は魔法の力でラクに働けるようになり、カラスになって親方から魔法をおそわる日々が続く。しかし、親方との恐ろしい契約は、どうやらそれだけではないらしい。なんと一年に一人職人達が死んでゆくのだ。クラバートに親切にしてくれたトンダ、そして落ち着きのあるミヒャルも死んでいく。そんな虜の生活の中で、クラバートは一人の少女と出会う。そして、この囚われた生活から彼を救い出してくれる方法は、彼女がクラバートに会いにきて、彼をえらんでくれることだということを知る。はたしてクラバートの運命は・・?
まるで終わらない夢のなかでずっと働いているようなこの物語。 読んでいる間中時間軸がずれていくような不思議な感覚に襲われました。霧の漂う湿地。カラスに変身して行われる魔術の授業。時々現れる、親方のまたその親方である男の不気味さ。彼がくる夜にひきうすですりつぶすのは、人の骨・・?!そして、一つずつ増えていく、湿地の墓と棺桶。この水車小屋での労働は、生身の身体で行うものではないらしい。みんなで働くこと自体は苦痛を伴うものではないらしい。身体も疲れないし、困ったことがあっても、ちょっと魔法を使えばうまくいってしまうし。なにしろ、この時代の一番重要な「食べること」には困らないんだから・・。でも、その代償として大きすぎるものをクラバートたちは親方に与えてしまう。それは自由と、命と、それから誰かと愛し合うこと。好きな女の子ができても、とことん黙っていろと言ったトンダは、やはり愛を親方に潰された人だった。みじろぎもしないで彼女を思うトンダとともにいる時に聞いた、どこからともなく聞こえてきた歌声。それがクラバートの愛する人・・・。すべてがモノトーンのなかにうずもれているようなこの物語の中で、この自分の可愛い人とふれあう時だけ、色づいているような美しさが溢れます。それは、語りかける声だけでかわすような恋です。でも、暖かい命そのもののような彼女の存在が、この魔術も親方の陰謀も、恐ろしい束縛も、すべてを吹き飛ばしてしまう力になる。この大いなる女性の力。
「心の奥底からはぐくまれる魔法」が解き放ったクラバートは、魔術も使えず、もう自分の力だけでいきていくことになる。でも、クラバートには、それは苦痛ではないはず。自由と愛を手にいれたんだから。そう。どうせ囚われるのなら、魔法にではなく、愛に囚われたいよなあ。
この物語は、古い民話がベースになっているらしい。やはり民話というのは、その土地がもつ、そこから生まれた幻想だけが持つ深さがあります。人が心の底に持つ、古い古い記憶の中で発酵している積み重ねられた思いは、夢の中で響く歌声のように、懐かしくて人を虜にする。
幻想を色濃く反映しながら、長い時間をかけて書かれたこの物語は、緻密な構成と筆力で、見事な幻想溢れるファンタジーになっています。それぞれのシーンが美しいんですよ。様々な光景が流れて、自分の中にしみこんでいくようです。この世界を見事に表現したヘルベルト・ホルツィングの挿し絵もこよなく魅力的。宮崎駿監督も、この物語から多くの着想を得ているそうです。
「千と千尋」のラスト、千尋が豚のなかから両親を選ぶシーンなんて、まさしくそうだなあ。魔女と契約して働く、というのもやはり同じだし。この物語と映画を比較しながら読んでも面白いかも。面白くてそんなこと忘れてよんじゃいましたが。オトナの人むけのファンタジー。とっぷり幻想の気配とゾクゾクする怖さを味わいたい人に。
by ERI
