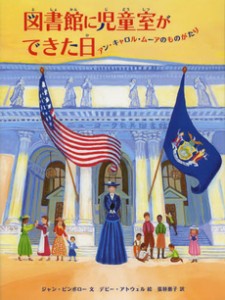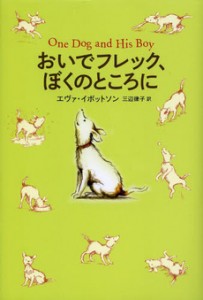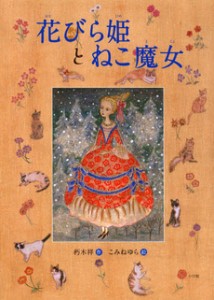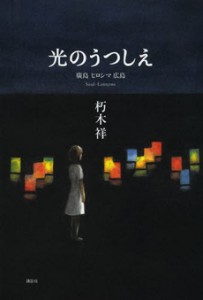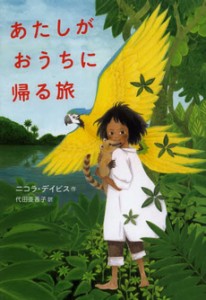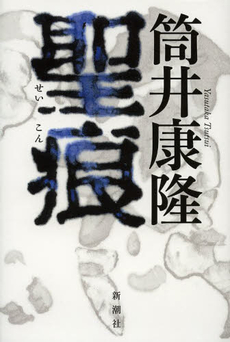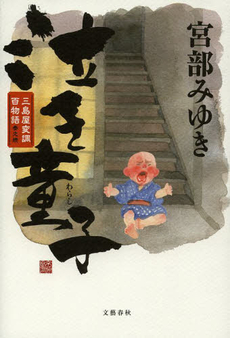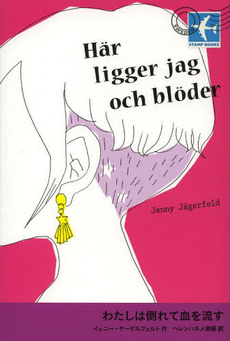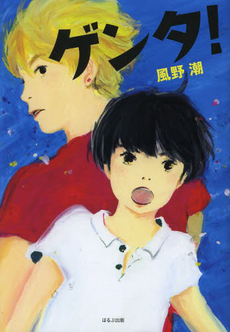ある日いきなり、自分の子どもが「あなたの実子ではない」と告げられたら。 是枝監督もこの赤ちゃんの取り違えをテーマにして映画を撮っていましたが、この「もうひとりの息子」の設定はもっと過酷です。何しろ、赤ん坊は片方はイスラエル、片方はパレスチナという反目しあう国の間で取り違えられてしまったのだから。この映画は、思いもよらない状況に放り込まれてしまった二組の親子を描いた物語です。
ある日いきなり、自分の子どもが「あなたの実子ではない」と告げられたら。 是枝監督もこの赤ちゃんの取り違えをテーマにして映画を撮っていましたが、この「もうひとりの息子」の設定はもっと過酷です。何しろ、赤ん坊は片方はイスラエル、片方はパレスチナという反目しあう国の間で取り違えられてしまったのだから。この映画は、思いもよらない状況に放り込まれてしまった二組の親子を描いた物語です。
イスラエルとヨルダン川西岸地区のパレスチナというと、かってのベルリンの壁よりも超えがたい壁が幾重にも重なっているように思います。現実として、そこには鉄条網が張り巡らされた分離壁がそびえ立っていて、映画の中で何度もクローズアップされて映し出されます。恥ずかしながら、私自身初めてこの映画でその分離壁を見たのですが、まるで「国」や「宗教」という大きな枠組みの超えがたさの象徴のように延々と、全く向こう側が見えないほどに高くそびえ立っているのに圧倒されました。しかし、この映画は、その何とも如何しがたい壁を超えようとする物語なのです。
この映画は、二組の親子がいきなり我が子の出生の秘密を告げられるところから始まるのです、その受け止め方が母親と父親では全く違うのが印象的です。同じ部屋に集められ、初めてお互いの顔合わせをしたとき、父親同士はまるで縄張りで出会った犬のように牙を剥きあうのだけれど、母親はただ見つめ合っただけで、お互いの胸にある辛さと苦しみを認め合うのです。ひたすら抱いて、ご飯を食べさせて、病気のときは胸もつぶれんばかりに心配して看病して。たとえ宗教がなんであろうと、どんな言語を話そうと、その母としての営みや赤ん坊を一人前にするときの苦労や喜びのあり方は同じなんですよね。お互いの瞳の中に苦しみを認めあったとき、苦しみがその愛情から生まれているものだということが理屈ではなく伝わってしまう。その共感が、同じように自分の胸にも伝わってくるのがわかりました。
2011年にノーベル平和賞を貰ったリーマ・ボウイーさんの自伝を読んだとき、男たちがいつまで経っても出来なかった停戦を、女たちが短期間に実現させてしまったことが書かれていたのを思い出します。イスラエル人として生きてきたヨセフは、ユダヤ教のラビにユダヤ人としての自分を否定されてしまう。そして、パレスチナ人として生きてきたヤシンは、分身のように仲が良かった兄に、いきなり敵視されてしまう。お互いのアイデンティティが揺らぐ日々の中で、ただひたすら手を差し伸べる母親がいるということが、二人の息子を支えていくんですね。そして、若者の心にお互いに対する共感と、一歩を踏み出そうとする勇気が芽生えます。
国家とか宗教とか。絶対に超え難いと思うものを、ただ一人の人間として向き合ったもの同士だけが超えていく。基本はここだな、と。人間は時代や国家との関わりから絶対的に逃げられない存在です。でも、物語は「個」を徹底的に描ききることでその縛りを唯一超えられるのではないのか。そこに、おとぎ話ではない希望が見いだせないか。脚本だけに3年かけ、国籍を超えて様々な国のスタッフとキャストをそろえてこの映画を撮影した監督の心にある願いが、非常に胸を打つ映画でした。