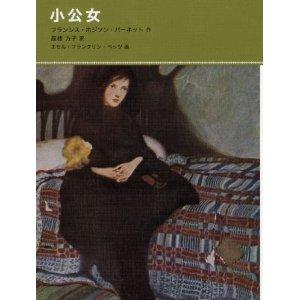表題になっている『白い人びと』は、8年前に、文芸社から『白い人たち』として翻訳出版されているのを読んだことがある。そのときにも、非常に幻想の気配が強い作品だと面白く読んでいたのだが、今回再び読んで、ますます魅了されてしまった。この8年の間に、私もますます〈あちら〉よりになっているのかもしれない。
表題になっている『白い人びと』は、8年前に、文芸社から『白い人たち』として翻訳出版されているのを読んだことがある。そのときにも、非常に幻想の気配が強い作品だと面白く読んでいたのだが、今回再び読んで、ますます魅了されてしまった。この8年の間に、私もますます〈あちら〉よりになっているのかもしれない。
この物語の魅力は、スコットランドの茫々たる荒野にある。人間の主人公はイゾベルなのだが、彼女の役割は、人里離れた荒野と一体化し、その魅力をあまねく味わいつくすことにあるような気さえする。その年頃の少女の一般的な楽しみとはかけ離れた、荒野から生まれた精霊のような少女なのだ。イゾベルは、人里離れた厳めしい城に住んでいる。彼女が生まれたときに両親は死んでしまった。それからずっと親族の大人二人と住んでいるのだが、彼女の住んでいるそこは、まことに浮世離れしたところなのである。霧がヒースやエニシダの間に満ち、様々に形を変える荒野に囲まれた城。そして、幼くとも一族の長であるイゾベルには、専用の笛吹きがいたりする。バーネットの荒野の描写は冴えに冴えて、まさにこの世のものならぬ気配を湛えている。ここではない、どこか。あちらとこちらの狭間にあって、もやもやと二つが混じり合う場所。例えば、マイケル・ケンナの写真集や、内田百閒の『冥途』とかにもつながる〈あちら〉だ。ただ、面白いのは、イゾベルがあまりにも自然に、その〈あちら〉側にいることなのだ。さっきイゾベルが生まれたときに両親が死んでしまったと書いたが、正しくはイゾベルは仮死状態になった母親から生まれてくるのだ。彼女は、誕生のときから深く「死」に結びついた存在なのである。
イゾベルは、幼いある日、荒野で白い人たちに出会う。それは、まさに闘いの場から帰ってきたばかりの人々で、その中にいた幼い「小さな褐色のエルスペス」とイゾベルは友達になり、一緒に遊んだりするのである。しかし、その小さな友人が見えるのは、実はイゾベルだけなのだ。しかし、彼女にとっては、あまりに自然に彼らがそこにいるものだから、イゾベルは彼らがこの世のものならぬ人たちだとは気付かない。あらゆる場所で、イゾベルのすぐ近くに佇む白い人たちに、彼女は全く畏れを抱くことがない。人里離れた場所で、荒野と書庫を相手に暮らしているイゾベル。生身の人間よりも「白い人」に近しい彼女が、荒野と書物に非常に高い親和性をもっているということが、私にはとてもしっくりくる。
彼女は白い霧の向こうに耳を澄ます感受性を持つ人であり、古い書物に埋没することを喜びとする人。それは、根をたどれば同じことなのだと思うのだ。自然の声を聞くことと、書物の中の人間の営みに心を浸すことは、同じ波長の中にある。土地には、土地の声がある。優れた感性を持つ人たちは、その土地の声を聞く。例えば先日買った梨木香歩さんの『鳥と雲と薬草袋』などを読んでいると、ひとつの場所から、一つの地名から、梨木さんがどれほどの声を聞き取っているのかに、心がしんとする。いつまでもその頁にいたくなる。だから、全く読み進まないのだけれど。いしいしんじさんの本を読んでいても同じことを思う。いしいさんにとってどこに暮らすかは、彼の精神と深く結びつくテーマなのだ。そして、例外なく梨木さんもいしいさんも、〈あちら〉と〈こちら〉を超える、書物の人でもあるのだ。一族の族長であるイゾベルの血の中には、そこでずっと暮らし、一族の歴史を積み上げてきた時間が理屈ではなく堆積している。そして、書物に心を浸すということも、今、目の前にいない人たちの声を聞く営みだ。例えば、私が『小公女』の主人公、セーラ・クルーに対して抱く想いは、見知らぬどこかの誰かに対するものではない。セーラは、どこにいるよりも彼女のそばにいることが安らぎだった幼い頃からの私の親友なのだ。イゾベルにとっての「小さい褐色のエルスペス」への想いは、私にとってのセーラのようなものなのだろう。実際に、長じて後、イゾベルは書物の中に「小さい褐色のエルスペス」を見つけることになる。
そう思うと、この物語の中の「白い人」も、私たちが想像する幽霊とは、どこか違う存在のようなのだ。彼らはごく当たり前に生者のそばに佇んでいる。そして、ひたすらな愛情を寄り添う人や、自分の音楽に捧げているのだ。荒野を笛吹きのファーガスが意気揚々とやってくるシーンなどは、まさに喜びに溢れている。つまり、彼らは夢のような儚さを湛えてはいるけれども、「死」の昏さに囚われたものではなく、どこか憧れに繋がるような仄かな光を湛えた存在なのだ。その憧れは、後半、ヘクターとミセス・マクネアンという美しい親子と出会うことによって、ますます深まっていくことになる。このバーネットが生み出した物語世界では、自然も、過去に生きていた人たちも、「今」を生きるイゾベルも、すべてが等価に、存在している。私はそこに魅了されてしまうのだ。死も、生も、土地も、自然も、すべての則を超えてこの物語の中でひそやかな美しい会話を交わしている。その声をバーネットの言葉を通して聞くのは、〈あちら〉の気配がする物語に惹かれがちである私にとっては至福の時間であった。
実は、この作品の献辞は、十五歳で夭折してしまった息子のライオネルに捧げられている。この作品の後半、死は恍惚感を伴うほどの甘美さで、荒野の美しさと重ねられていく。それは、もしかしたら、生き残ってしまったバーネットが、その時強烈に息子が囚われた「死」に惹かれていたからかもしれない。実際読んでいても、あまりにも死が近しく甘美に語られるので、面喰ってしまうところもある。でも、だからこそ、この物語はバーネットにとって書かねばならないものだったのかもしれない。柳田邦夫さんがご子息を亡くされたとき、「書く」ということが一番自分の救いになったとおっしゃっていた。想像にすぎないが、やはり「書く人」であったバーネットもそうだったのかもしれないとも思う。この本には、『秘密の花園』のコマドリを思わせるエッセイ、「わたしのコマドリくん」や、バーネットが幼い息子たちに話して聞かせたような、「気位の高い麦粒の話」、庭に対する愛情を書いたエッセイの「庭にて」も収められている。エッセイは、大好きな『秘密の花園』に繋がるモチーフについて書いたもので、とても興味深かった。バーネットが愛したものたちが、この本にはいっぱい詰まっている。バーネットの作品に深い思い入れがある私にとっては、まことに堪えられない一冊だった。
余談だけれど、この八月に、友人と夏の旅行に行く予定を立てている。そこで、満月の夜に湿原を歩くという体験をしてみようと思っているのだ。イゾベルが月夜の荒野で体験した幽体離脱のような体験が出来るかも―というのは、無理だけれど。この物語を読みながら、ワクワクしてしまった。私にも、遥かな自然の声が聞こえますように。
2013年4月発行
by ERI