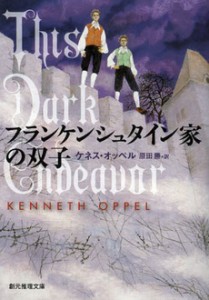
「何と、あの人造人間を作ったフランケンシュタインが、双子だった!」と、思わずびっくりマークをつけたくなる設定で描かれた小説です。ケネス・オッペルはいつも設定が斬新なんですが、この人造人間を作る以前の、YA世代のフランケンシュタインを描くという発想が面白い。中世の錬金術のおどろおどろしさと、主人公たちの若い激情が迸って、極彩色のゴシックホラーになっています。
フランケンシュタイン家の双子、コンラッドとヴィクター。正反対の性格ながらとても仲良しの二人だが、ある日兄のコンラッドが重い病で倒れてしまう。何とか彼を助けたいと思うヴィクターと、彼らと一緒に暮らしている遠縁の娘・エリザベスは、城の地下から発見した錬金術の本を読解しようと錬金術師ポリドリを探す。ポリドリは、その本を解読し、不死の秘薬を作るために三つの材料が必要だと言う。ヴィクターとエリザベスは、その材料を集めるために命がけの冒険に乗り出すのです。
いきなりヴィクターがベランダから落っこちる冒頭の劇中劇から始まって、とにかくケレン味たっぷりなんですよね。錬金術の本を城の地下で見つけるシーン一つにも、隠し扉&底の見えない階段&白骨&腕をはさんで抜けない扉・・・と、もう、これでもかとてんこ盛りの演出なんですが、それが上手く登場人物たちのキャラクターに馴染んで展開していくのが、オッペルの腕ですね。想像力が刺激されて、次々と物語の迷宮を進みたくなる。その中で展開していく双子の弟・ヴィクターの揺れ動く心が、また読みどころです。
兄のコンラッドは双子で顔もそっくりなのに、冷静沈着で人づき合いも上手く、剣の腕もヴィクターより上です。しかも、一緒に暮らす美しいエリザベスの愛まで手に入れている。ヴィクターにとって兄は一番強い絆の持ち主であり、同時に激しく対抗意識を燃やすライバルでもあるのです。その兄のために、自分の命までかけるような冒険に乗り出していくヴィクターの胸は、冒険で流す血よりも濃い感情、嫉妬と愛情で揉みくちゃ。しかも、双子の間に君臨する女神のようなエリザベスの、小悪魔っぷりったら・・・ラノベのツンデレの比じゃありません(笑)野生の血がたぎるような魔性の女、しかも無自覚というのが、また始末に悪い。(これ、凄く褒めてます・爆)深い森の奥に生えるコケをとりに、月のない夜の中を秘薬でオオカミの目になって進むエリザベスとヴィクター。記憶の奥深くから蘇る野生にあぶられるような二人の姿が、美しくて官能的です。恋人であるコンラッドには決して見せない残忍さや激情を、エリザベスはヴィクターの前では無防備に全開にするんですよね。それは、絶対的に自分を愛している男に対して女が見せる甘えと残虐さでもあるんですが、こういう恋愛の駆け引きでは、16歳の少年なんて女に勝てるわけがない。夢遊病であるエリザベスが、ヴィクターのベッドに入ってくるシーンなんて、もう気の毒としか言いようがない感じ。そらなあ、もう骨抜きになるわなあ、と思わずヴィクターへの同情を禁じ得ないエリザベスの魔性っぷりです。オッペルは魅力的な少女を書く人ですが、この多重性をあらわにするエリザベスの美しさは格別です。彼女はこの物語の起爆剤。いやもう、ヴィクターは気の毒なほど頑張ります。しかも、三つの材料の最後は・・・これは、ネタばれになるんで書きませんが、えっ、そこまで!と思う大きな犠牲をはらうものなのです。(また、このときのエリザベスが凄い。サディズムの気配まで漂います)
このシーンを読んで、なぜこれがYA向けではなく、創元推理文庫で出たのか納得しましたが。どんなに心が揺れても、ヴィクターはとことんコンラッドを助けようとした。ワシと闘い、地底の奥深くに潜り、しかも最後には自分の命さえもかけてコンラッドの病気を治そうとした。彼が愛憎に揺れ動きながらも、いや、だからこそ、その気持ちを貫いた姿に胸打たれます。だからこそ、ラストでその彼が失ってしまったものの大きさに胸をえぐられるのです。大きな犠牲を払った上に大切な存在を失い、もしかしたらそれが自分のせいかもしれないと思ってしまったヴィクターが、これからどんな道を歩むのか。とても気になりますが、訳をされた原田さんの後書きによると、続編翻訳中だとか。楽しみにして待っていようと思います。
2013年4月刊行
東京創元社
