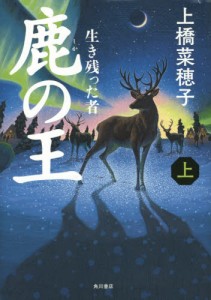昨日思い立ってブログのタイトルを少し変えてみた。何のブログか明確にするためにと、少しでも検索ワードに引っかかるとよいな、という計算からだが(笑)好きな作品を、好きだ!と書くというスタンスは変わらない。この作品も、表紙を見ただけで「好きかも」と思った予感が当たって、とても素敵な本だった。
昨日思い立ってブログのタイトルを少し変えてみた。何のブログか明確にするためにと、少しでも検索ワードに引っかかるとよいな、という計算からだが(笑)好きな作品を、好きだ!と書くというスタンスは変わらない。この作品も、表紙を見ただけで「好きかも」と思った予感が当たって、とても素敵な本だった。
まず、文章がとても心地良い。この物語は、ゆいという少女が思春期の入り口に立って迎える、小さなターニングポイントを描いたものだ。急に背が伸びて、今まで気にしなかった異性も、少し気になったりする。自分でももてあますほどの大きな波がやってくる前の、体の中がざわめくような季節が、一年の自然の移り変わりと共に描かれる。ゆいと一緒に、柔らかな命の気配にふんわりと包み込まれるような心持ちになった。
そう、この物語に満ちているのは、様々な命の気配だ。まず、仲良しの姉であるまいの妊娠。「おねえちゃん」が迎える様々な変化に、まいは戸惑う。妊娠しているときというのは、自分であって自分ではない、「あたしの体は今、ちびちびちゃんが操縦しているようなもんだよ」という時間なのだ。植物たちが一斉に芽吹くような命のたくましさへの畏怖のような気持ちを、ゆいはお腹が大きくなっていく姉とともに体験する。そのたくましい命は、目覚め始めたゆいの心と体にも芽吹いているものなのだ。
もう一つは、ゆるやかな時の流れの中に溶け込んでいる、耳を澄ませないと聞こえない遙かな命の気配だ。学校にあるゆいのお気に入りの月野池には、河童の主がいるという。ゆいには、幼い頃にここで出会った不思議な少年との大切な思い出があった。千年を生きる木々や森たちのように、自分とは違う時の流れの中にいる存在を感じ取る力が、ゆいにはある。目には見えないものを見る感受性は、やはり河童と出会う『かはたれ』(朽木祥、福音館書店)の麻のように、美を感じる心、何者にも侵されない心の羅針盤を持つことに繋がっていく。だから、ゆいの奏でるピアノの音には、人の心を揺さぶる力があるのだと思う。
今生きているということと、自分が遙かな時の流れの中にいるということは、同じことなのだ。刹那と永遠をこの身にいだく、命の不思議への畏怖と敬意が、ゆいという少女の日常から素直に伝わってくるこの物語は、木々が緑に染まっていく今の季節にぴったりだと思う。
2014年11月刊行