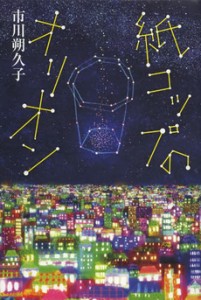特定秘密保護法案が強行採決された。なぜ、そんなに急いであの穴だらけの法案を通さなければならないのか。世論の反対を押し切っての強行採決に非常に不安を覚える。憲法改正の動きといい、中高年御用達の週刊誌が煽り立てている反中韓キャンペーンといい、ここ最近のきな臭さといったらどうだろう。昨年の自民党の圧勝から不安に思っていたのだが、一斉になだれを打って一つの方向になびいていくこの空気が恐ろしい。しかも、こんな風に考える自分はえらくマイノリティであるようなのだ。ずっとのしかかる重いものを抱えている中で、この映画の予告を見て、「これは見にいかねば」と思ったのだが、なんと梅田ガーデンシネマでは珍しい立ち見まで出る混雑ぶりに驚いた。岩波ホールでも連日満員だそうである。嬉しい驚きだった。もしかしたら、私のような不安を抱えている人間は、多数派とはいかぬまでもそこそこいるんじゃないか。どんな非難にも負けずに真実を主張したハンナの姿とともに、少し勇気づけられた午後だった。
特定秘密保護法案が強行採決された。なぜ、そんなに急いであの穴だらけの法案を通さなければならないのか。世論の反対を押し切っての強行採決に非常に不安を覚える。憲法改正の動きといい、中高年御用達の週刊誌が煽り立てている反中韓キャンペーンといい、ここ最近のきな臭さといったらどうだろう。昨年の自民党の圧勝から不安に思っていたのだが、一斉になだれを打って一つの方向になびいていくこの空気が恐ろしい。しかも、こんな風に考える自分はえらくマイノリティであるようなのだ。ずっとのしかかる重いものを抱えている中で、この映画の予告を見て、「これは見にいかねば」と思ったのだが、なんと梅田ガーデンシネマでは珍しい立ち見まで出る混雑ぶりに驚いた。岩波ホールでも連日満員だそうである。嬉しい驚きだった。もしかしたら、私のような不安を抱えている人間は、多数派とはいかぬまでもそこそこいるんじゃないか。どんな非難にも負けずに真実を主張したハンナの姿とともに、少し勇気づけられた午後だった。
ハンナ・アーレントはユダヤ人の高名な哲学家だ。戦時中はユダヤ人の青少年をパレスチナに移住させる仕事をしていた。フランスで国内収容所に収容され、何とか脱出したあとアメリカに亡命し、そこで『全体主義の起源』を書いて名声を獲得する。しかし、1960年にイスラエル軍が逮捕したアイヒマンの裁判を傍聴し、ニューヨーカー誌に連載した『イェルサレムのアイヒマン』が世論の猛反発にあう。何百万人ものユダヤ人を収容所に送り虐殺した稀代の極悪人として裁判にかけられたアイヒマンが、実は何も考えずに言われたまま任務を遂行しただけの凡庸な人間であったこと。そして、当時ナチスに協力したユダヤ人の指導者達がいたことを指摘したためであった。彼女はそのために長年の友人を失い、孤独の中に叩き込まれる。しかし、彼女は一歩も引くことがなかった。アイヒマンの凡庸さの中にこそ、思考停止という最大の悪が潜んでいると確信していたからだ。この映画は、アイヒマンが強制連行されるシーンから始まり、非難の嵐の中で孤独に戦うハンナの姿が描かれる。
思考停止と悪というテーマで思い出すのは、高村薫の『冷血』だ。ネットの掲示板で出会った男たちが、さしたる動機もなく歯科医の家族を惨殺する。徹底的な警察の検証をもってしても、そこには犯行に繋がる「なぜ」は見つからない。彼らは言う。「考えていたら、やってません」と。何とアイヒマンと似ていることか。彼らは思考停止の虚無の中に自分を放り込み、ただ身を任せただけなのだ。この映画ではアイヒマンは役者が演じておらず、実際の裁判での映像が使われている。話し方といい、その情けない風貌といい、「ああ、知ってるわ、こんな人・・・」と思うようなただのオジサンなんである。「世界最大の悪は、平凡な人間が行う悪なのです。そんな人には動機もなく、信念も邪心も悪魔的な意図もない、人間であることを拒絶したものなのです」 これは映画の中でハンナが学生に講義する一節だが、実際のアイヒマンの映像はその主張を見事に裏付けていた。
この思考停止が、当時のドイツの官僚たちだけではなく、ドイツに対抗するべき連合国側にもはびこっていたことは、エリ・ヴィーゼルが『死者の歌』の中で述べている。ナチス政権はユダヤ人における虐殺を一気に行ったわけではなく、段階を踏んで小出しにし、諸外国の反応を伺っていた。しかし、そのどの段階においてもさしたる反応は見られず、ナチス側はこれを「了承」と見なしていった。『サラの鍵』(タチアナ・ド ロネ)で当時ナチスに反目していたはずのフランスでもユダヤ人の強制収容が行われていたことが世界に知られるようになったが、つまるところユダヤ人たちは「傍観者の無関心」(『死者の歌』)の中で四面楚歌の状態だったのだ。この思考停止は、まさに何百万人という大虐殺を引き起こしたが、その中枢にいた人物がまさに平々凡々たる一市民であったことは、今、私たちが肝に銘じるべきことだと思う。中国を占領していた時代の日本人将校の回想を読んだことがあるが、彼らはアイヒマンと同じことを言っていた。曰く、自分たちは命令されてやっていただけなんだと。ただ真面目に任務を遂行しただけなんだと。「真面目」という美徳が、戦争において発揮されてしまうとそれは無制限のやりたい放題になってしまうのだ。思考停止という『冷血』は、特別な人の中にのみ存在するのではない。それは、人間という存在が常に抱える、誰もが孕んでいる最大の悪に繋がるものなのだ。
そう考えたとき、まるでザルのように政権に無制限な秘密保持の権限を与える法案を強行採決してしまう安倍政権は非常に危険な存在であると思わざるを得ない。政権を握る側が一方的に秘密を指定でき、それを国民が知ろうとするだけでも懲罰の対象になるという法律が、恣意的に運用されない保障など、どこにもない。彼を「支持する」と答える大多数の人々の支持理由は、アベノミクスという、株価の上昇と円安という経済的なものだと思われる。要は金だ。私には、彼らが「あんたらは株価だけ見ときなはれ。そのほかのことは、わしらが上手いことやっといたるさかい」と国民の耳と口をふさぎにかかっているとしか思えない。彼らがこの強行採決の影で何を考えているのか、もっと目を懲らしてしっかり見ていないと大変なことになるのではないだろうか。人間は誰一人として全知全能な存在ではない。だからこそ、細心の注意を払って、悪が生まれる可能性をつぶしておかねばならないのだ。ハンナはこの映画のラストで疲れ切って自宅の窓から町を見下ろす。パンフに早乙女愛氏も書いておられるが、そこには摩天楼の夜が広がっているのだ。夜の都会の風景は、今、どこの国もさして変わらない。ハンナを包む夜の孤独は、今、私たちの周りにも広がっている。この映画はそのままでいいのか、と見る者に強く語りかけているようだった。ハンナは「思考」とは「自分自身との静かな対話」だと言う。その行為に「書物を読む」という行為は深く関わっていると私は思う。子どもたちにどうやってその行為を手渡すのか。そのことについても、また深く考えさせられる映画だった。