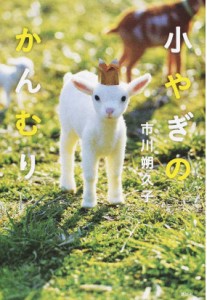浅草を舞台に、人力車を引いている「吉瀬走」という少年を軸にした連作短編の二作目。「力車屋」の男たちや、そこにやってくる客の視点で一話が描かれる。走は両親の蒸発、という事情があって一人で力車屋にやってきた。他の男たちも、何かありそうなんだが、一作目ではあまりわからずにいた。この「わからない」というのもミステリアスでいいのだが、この二作目では少しずつ彼らの事情がわかっていくのに、ときめいてしまう。いきなり間合いをつめるのではなくて、この連作のように、人とも小説ともゆっくり知り合うのが好きだ。そして、二作目まできて、前作にぼんやりと感じていたことが、ますますくっきりしてきた。それは、この物語が、去るものと去られるものが複雑に交差する物語だということだ。
浅草を舞台に、人力車を引いている「吉瀬走」という少年を軸にした連作短編の二作目。「力車屋」の男たちや、そこにやってくる客の視点で一話が描かれる。走は両親の蒸発、という事情があって一人で力車屋にやってきた。他の男たちも、何かありそうなんだが、一作目ではあまりわからずにいた。この「わからない」というのもミステリアスでいいのだが、この二作目では少しずつ彼らの事情がわかっていくのに、ときめいてしまう。いきなり間合いをつめるのではなくて、この連作のように、人とも小説ともゆっくり知り合うのが好きだ。そして、二作目まできて、前作にぼんやりと感じていたことが、ますますくっきりしてきた。それは、この物語が、去るものと去られるものが複雑に交差する物語だということだ。
それを象徴するのが、冒頭の「つなぐもの」だ。この物語は、走という少年が母に置き去りにされてしまうところから始まる。いつも、そこにあると思っていた日常。部活をして、ご飯が用意されていて、進学すると思っていた場所から遠く離れてしまった彼が見つけた居場所が、力車屋だ。しかし、この「つなぐもの」は、走に置き去りにされてしまった部活の仲間の少年遠間直也の視点から描かれている物語だ。走は、自分が去ったことが、これほど仲間たちの心に影を落としていることには気づいていないのだろう。この人間の立体感を短編連作という形で見せてくれるのが、この物語の面白いところだ。人は、案外自分が人にどんな波紋を投げかけているのか、知らぬまま生きている。
「ストーカーはお断りします」「幸せのかっぱ」「願いごと」「やっかいな人」「ハッピーバースディ」と、その他に五つの短編が収められていて、走や力車屋の人たちのところに様々な人たちがやってくる。走たちも彼らも、大切な人や、当たり前にそこにあると思っていた場所を失ったり、無くしかけている人たちだ。しかし、つかの間、走たちの車に乗り、いつもと違う場所から自分を眺めて、笑顔を一つ抱えて帰っていく。その笑顔がまた、走たちの心を動かしていく。そのダイナムズムをとらえる作者の目は鋭くて優しい。人はそれぞれの人生を、それぞれの速度で駆け抜けていく。親子や夫婦でも、全く同じ歩調で歩く、などということはできないし、いつも何かを置き去りにしたり、失ったり、ぐるぐる堂々巡りしたりしながら生きている。この力車屋に集まっている面々の顔ぶれも、心のありようも、数年後には変わってしまっているのだろう。この物語の底に流れている切なさは、かけがえのない「今」が鮮やかに刻印されているせいではないだろうか。
最後の「ハッピーバースディ」で、走は自分を捨てた母から自分の意思で旅立っていく。縁も人との関係も、失ったものも、またそこから初めて自分で掴んでいけばいい。このシンプルな願いにたどり着くまでの走の心の軌跡が、人力車の轍のように鮮やかに胸に残って切なく、後悔だらけの人の生が愛しくなる。「やっかいな人」で、1の冒頭に出てきたミュールの女の子が出てきてしまったから、「車夫」はもうこれで終わりなんだろうか。「3」が読みたいなと、もう思っているのだけれど。
あと、これは余談だが、前作からずっと高校生という年齢の子たちのセーフティネットについて気になっている。走の場合は事業に失敗した父親がまず蒸発し、生活に行き詰まった母親も走を置いていなくなった。私学に通う走は学費も払えなくなり、家賃も生活費もなく一気に行き場を無くして途方に暮れてしまう。走は、先輩の前平くんが力車屋に連れてきてくれたから良かったものの、いろんな理由で親を頼れなくなる高校生は、きっととても多いのではないかと思うのだ。人と人との繋がりが薄くなり、自己責任という冷たい言葉が大きな顔をしている今、相談したり、頼ったりできる大人が身近にいる子は少ないだろう。そして、見た目は大人に近い高校生の子たちを食い物にしようとする闇は、あちこちにぽっかりと口を開けているはず。彼らの困難を捨て置いて、いいはずがない。いとうさんのこの作品はそういう社会に対する一つの問いかけでもあると思う。