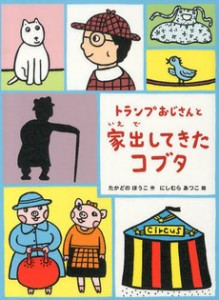もう5年ほど前になるんですが、当時はまだ外に遊びに出していたうちの猫が、数日の間行方不明になったことがあります。いつもなら名前を呼べば帰ってくる子が夜になっても帰らない。さあ、そこから私がどんなにうろたえたか、苦悩の数日間を過ごしたかは、興味のある方は当時の日記をお読み頂くとして-靴下を何足も履き破ってしまうほど愛猫を探し歩きながら、ずっと考えていたことは、「なぜ、ぴいすけじゃなきゃダメなんだろう」ということでした。早朝や夜に猫のいそうな場所を探しながら歩いていると、飼い猫やら野良さんやら、たくさんの猫に出会います。その度に「うちの子じゃない」とがっくりし、狂おしいまでに自分の猫をこの手で抱きたいと思った、あの渇望。猫はこんなにたくさんいるのに、どうして私はあの子でないとダメなんだろうと、よその猫を見るたびに苦しいほどに思ったあの気持ちを、この絵本を読んで久しぶりに胸をつかまれるほど思い出してしまいました。
もう5年ほど前になるんですが、当時はまだ外に遊びに出していたうちの猫が、数日の間行方不明になったことがあります。いつもなら名前を呼べば帰ってくる子が夜になっても帰らない。さあ、そこから私がどんなにうろたえたか、苦悩の数日間を過ごしたかは、興味のある方は当時の日記をお読み頂くとして-靴下を何足も履き破ってしまうほど愛猫を探し歩きながら、ずっと考えていたことは、「なぜ、ぴいすけじゃなきゃダメなんだろう」ということでした。早朝や夜に猫のいそうな場所を探しながら歩いていると、飼い猫やら野良さんやら、たくさんの猫に出会います。その度に「うちの子じゃない」とがっくりし、狂おしいまでに自分の猫をこの手で抱きたいと思った、あの渇望。猫はこんなにたくさんいるのに、どうして私はあの子でないとダメなんだろうと、よその猫を見るたびに苦しいほどに思ったあの気持ちを、この絵本を読んで久しぶりに胸をつかまれるほど思い出してしまいました。
花びら姫は、五月のばらよりも綺麗なお姫様。自分の美しさをよーく知っているお姫様は、「とくべつ」なものだけを求めて、家来たちに集めさせておりました。ところが、ある日妖精たちのパンケーキをつまみ食いしてしまったせいで、花びら姫は恐ろしい呪いをかけられてしまい、凍える寒さの北の森にある石の館に、ムカデやカエルと住むことになってしまいます。その呪いを解くには、「とくべつ」な猫が必要。そこで、呪いのかかった花びら姫、つまりねこ魔女は、そこら中から猫を探してさらってきますが、手当たり次第に集めたどの猫も、「とくべつ」ではないのです。その彼女に「とくべつ」を教えたのは、誰だったのか。「とくべつ」って何なのか。それが、この絵本のテーマになっています。
花びら姫は、誰も愛したことがなかったんですよね。愛したのは自分だけ。だから「とくべつ」がわからない。彼女が閉じ込められた北の森の館は、本当は誰も愛さなかった彼女の心の中だったのかもしれません。その彼女の凍てついた心を溶かしたのは、どこにでもある、でも、たった一つしかないもの。それは、私が、どうしてもぴいすけを抱きしめたいと思った気持ち。初めて抱き上げたときの柔らかさに感じた愛しさから始まって、毎日交わす眼差しや、寄り添う体温の中に育てているものに違いありません。私は、お散歩してるワンちゃんと飼い主さんを見るのがとっても好きですが、それはお互いを「とくべつ」と思っている気持ちを感じるからなんだと思います。あと、猫を猫可愛がりしている、もしくは猫に下僕のようにお仕えしている(笑)ベタ甘の猫ブログを見るのも、とっても好きなんですよね。猫という生き物は、人間に愛されれば愛されるほど猫らしく、「うふふ。私ってとくべつ」と輝いているように思います。猫が大好きでご自分も猫さんと暮らしておられる朽木さんとこみねさんは、そこがとてもよくわかってらっしゃる。ありふれているけれど、かけがえのないもの。日常の中にごく当たり前にあるけれど、本当はふたつとない大切なもの。この絵本は、そんな自分のそばにある「とくべつ」を教えてくれる。読み終わったあと、思わず自分のそばにいる可愛い子を抱きしめたくなる。自分の愛するものが、きらきらと輝いてみえる。そんな絵本です。
実は、この絵本に描かれている猫さんたちは、みーんな誰かの「とくべつ」なのです。ツイッターで、この絵本のために愛猫の写真を募集があったんです。2月ぐらいだったかな?もちろん、私もちゃんとうちの猫さんふたり、ぴいすけとくうちゃんの写真を送りました。こみねさんは、その全部の猫さんたちを、丁寧に丁寧に、一匹一匹この絵本に書き込んでくださったのです。なんと、全部で80枚以上の原画をお描きになったとか。うちの子たちも、ちゃーんとおります。「うちの子、わかるかなあ」と思っていたのが申し訳ないくらいに、一目見て「あっ、これ、うちの子!」とわかりました。それだけ、ほんとに愛情込めて書いてくださったんだと、もう感涙で、それからどれだけ人に自慢しまくっていることか(笑)自慢用の一冊を用意して、持ち回っています。きっと、私のように自慢しまくっている飼い主さんたちが、日本中にいますね。今、ざっと数えただけでも100匹近くの猫さんがこの絵本におりましたよ。凄い!だから、この絵本にはたくさんの、でも、たった一つしかない「とくべつ」が詰まっています。こみねさんの筆は、その愛情を感じ、朽木さんの描き出す心の物語に感応して、冴え渡っているようです。もう、隅々まで美しい。どの頁を見ても見飽きない。見れば見るほど引き込まれます。朽木さんの繊細な文章とこみねさんの絵の素敵なマッチング。「細部に神が宿る」とはこのことかと思いますね、ほんとに。
私はきっと、一生この絵本をそばにおいて、誰かれ構わず自慢しまくることでしょう。「また、はじまったで、ばあちゃんの自慢話」「何回聞かされたかわからんな、もう耳タコや」「もうしゃあないな、あれがたった一つの自慢なんやから、聞いたれや」と言われることでしょう。もし、将来孫なんかが出来たら、きっと嫌というほど読み聞かせてしまうに違いない。入手してから、枕元に置いて毎日眺めております。大好きな朽木さんのテキストで、大好きなこみねさんの絵の本に、うちの猫たちがいるなんて、これほど幸せなことはありません。この本は、私の「とくべつ」な一冊です。
2013年10月刊行
小学館