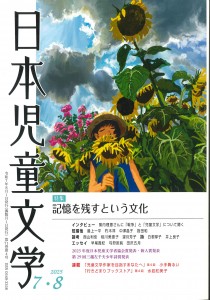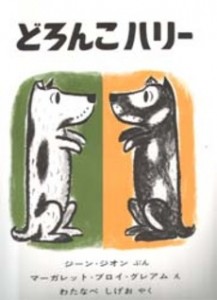今日(11月4日)は、関西ろうさい病院で、【いいお産の日】というイベントがありました。これは、かんさい労務病院のもとでいいお産をし、笑顔のあふれた家庭・社会を一緒に作るという目的で、毎年病院が行っている行事だそうです。そこで『子どもと絵本に親しむ』というテーマで、kikoさんがメインのお話を、私がサブでお手伝いを、という形で参加させて頂きました。
ブックスタート(赤ちゃんに初めての絵本をプレゼントする活動です。今、多くの自治体で行われています)のお仕事をしていてよく思うのが、「絵本」について、親ごさんたちが構える気持ちをもってらっしゃること。「いつから読めばいいのか」「どういう風に読めばいいのか」「どんな絵本がいいのか」漠然と、ルールを求めてらっしゃるように思えることがあります。でも、絵本を読むのにルールはいらない。いつから、どんな絵本を読んでもいいし、どんな風に読んであげてもいい。ルールのない自由さを楽しむのが絵本のいいところだと思っています。一番大切なのは楽しむこと。子どもと一緒に笑顔になれること。子ども時代にしか経験できない、かけがえのない親子の時間を過ごすことが、絵本のある一番の喜びだと思うのです。今日のkikoさんのお話も、実際に絵本を紹介しながら、絵本の楽しさ、絵本と共に過ごす子育ての楽しさについてのあれこれを紹介するという形で進みました。
そこで何組もの親子の皆さんや看護師の皆さんとお話をして思ったのが、「絵本の力」です。会場には、たくさんの本を持っていきました。(リストを固定バーの『おいしい本の特集』の頁に貼っておきます)そこでお話をしながら、または自由に絵本を見て頂いたのですが、皆さん絵本を見ると、とてもいい顔になるんです。「この本覚えてる!」「よくおふくろに読んでもらいました」というお父さん。お父さんたちに人気だったのが『どろんこハリー』です。
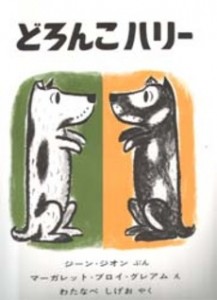
このハリーのやんちゃぶりが、お父さんたちの少年心をくすぐるのかも(笑)お父さんたちが、むっちゃ笑顔でした。この笑顔、っていうのがいいんですよねえ。そのお父さんたちの「まだあるんですね、この絵本」という言葉を聞いてはっとしました。
私たちは、図書館で働いていて、いつも身近に絵本があって、どれがスタンダードで長らく愛されている絵本なのかを一通り知っています。でも、大抵の若い親ごさんたちは、絵本に触れる機会が、子ども時代以降、ぷっつりないのです。だから『ぐりとぐら』という絵本を、中川李枝子さんと山脇百合子さんというゴールデンコンビが書いてらっしゃるということも知らない。「外国の絵本なんだと思ってました」という言葉に、こちらのほうが、そうか、それも当たり前なことだよなあと認識を新たにさせて貰いました。スタンダードでなくても、名作でなくてもいいんですけど、「この絵本素敵ですよ」「面白いですよ」といろんな形で紹介することって、やっぱり必要だなと思ったんです。
絵本には力があります。読み手を笑顔にする力。頭の中で、いっぱい想像という翼を羽ばたかせるイメージを生む力。「国語が出来るようになりますか?」ということを期待される親ごさんもいらっしゃるけど、それはまあ「そんなことがあったらいいな」くらいで置いといて(笑)何より、絵本を通じて、いっぱい親子でお話して欲しい。「ちょっと怖い内容の絵本を読んでも大丈夫なんですか」とおっしゃるお母さんもいらしたけれど、お父さんやお母さんのお膝や抱っこの中で、怖い世界を覗くのも、一つの経験だと思います。絵本の、物語のいいところは、ちゃんと帰ってこれるところ。最近流行りの『地獄絵本』なんかは、私はどうなんだろうと思いますが(だって、あれは絵本じゃないですからね。元々の目的が、信仰しないと地獄におちるよ、という脅迫のようなものですから。絵も美しくない)物語の世界を堪能して、また温かいお膝に戻ってくるというのは、これも大きな喜びです。
一人のお父さんが『おおきなかぶ』を見て、しみじみと「これ、おふくろがよく読んでくれたんですよ。うんとこしょ、どっこいしょ、ってすごく元気に読んでくれた声も思いだしました」とおっしゃってました。そのお母さんは、今、ご病気で声がうまく出せなくなってらしゃるそうで・・。でも、絵本を見たときに、元気な時のお母さんを、絵本を読んで、いっぱい抱きしめてくれたその愛情も一緒に思いだせるなんて、なんて幸せなことなんだろう。胸がいっぱいになりました。改めて、絵本っていいなあと思わせて頂けたこと。たくさんの気づきを頂けたこと。貴重な機会を頂きました。看護師長さんはじめ、お世話になった方々に、心から感謝の一日でした。また、こんなふうに、絵本のお話をいろんな方とできる機会があったらと思います。

by ERI
 太田女子高等学校新聞部発行の7月18日号「学友報知」にインタビューを載せて頂きました。 拙著である『戦争と児童文学』(みすず書房)を読んでくださったのがきっかけです。
太田女子高等学校新聞部発行の7月18日号「学友報知」にインタビューを載せて頂きました。 拙著である『戦争と児童文学』(みすず書房)を読んでくださったのがきっかけです。