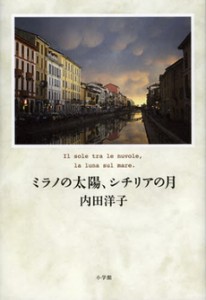 ここのところ、ずっとパソコンの不調に悩まされていました。ちゃんと立ち上がらないし、すぐに固まってしまう。あれこれやってみても埒が明かないので、とうとうリカバリしました。しかも、リカバリディスクを紛失してしまったので、F10連打からのリカバリという原始的(?!)な方法で。おかげで何とか動くようになったんですが、設定のやり直しやWindowsの膨大な更新やらで、時間と手間が半端なくかかりました。慣れないことをするというのは、ほんと大変です。その作業をしながら、この本を読んでいたのですが、こんなパソコンひとつでも右往左往してしまう私にとって、さらっと異国で家を買ったり、パーティを開いたりしてしまう内田さんは、それこそ遠い月を眺めるような遥かな憧れの存在です。
ここのところ、ずっとパソコンの不調に悩まされていました。ちゃんと立ち上がらないし、すぐに固まってしまう。あれこれやってみても埒が明かないので、とうとうリカバリしました。しかも、リカバリディスクを紛失してしまったので、F10連打からのリカバリという原始的(?!)な方法で。おかげで何とか動くようになったんですが、設定のやり直しやWindowsの膨大な更新やらで、時間と手間が半端なくかかりました。慣れないことをするというのは、ほんと大変です。その作業をしながら、この本を読んでいたのですが、こんなパソコンひとつでも右往左往してしまう私にとって、さらっと異国で家を買ったり、パーティを開いたりしてしまう内田さんは、それこそ遠い月を眺めるような遥かな憧れの存在です。
このエッセイは、『ジーノの家』に続くエッセイの第二弾。緻密な香り高い文章はますます冴え、10編のお話は、まるで巨匠が撮った映画のように鮮やかにイタリアの風景と人間を浮かび上がらせます。私は体質的にお酒があまり飲めないのですが、上質のワインを味わう楽しみというのはこういうものかしらと思わせられる、贅沢な文章です。異国人ならではの眼差しと、深くその国を理解する知力と教養。心に刻んだものを、ゆっくりと熟成させる時間。それが結びついた稀有な文章だと思うのです。イタリアという国で、凛と背筋を伸ばして仕事をし、人との出会いを大切にして生きてこられた内田さんの豊かさが、文章から溢れてくる。「六階の足音」という章に、谷崎の『陰影礼賛』の話が出てくるのですが、イタリアという歴史のある国ならではの陰影の濃さに心が震えます。50年間秘めた恋をやっと叶えた喜びもつかの間、病に倒れてしまう女性弁護士。狷介な夫との長年の確執の象徴のような古い屋敷を守り通す女性の孤独。読み書きを学ばないままに生きてきた老練な一匹狼のような船乗り。小さな駅舎でつましく暮らしながら、確かな幸せを築いた一家・・・人生という思い通りにならない旅を続けながら、彼らがなんと自分らしく背筋を伸ばしていることか。彼らの目に映るイタリアの空と海の色が、見たこともないのに心に映ります。たとえどんな場所にいても、イタリアのいい女は高いヒールの靴をはいて美しく装い、まっすぐ風を受ける。内田さんもそうでらっしゃるのかなと勝手に想像します。
そんな孤独と誇りが香るイタリアもとても美味しいけれど、へたれな私は、滅多にない幸せな風景に惹かれます。この10編の中で特に好きなのは「鉄道員オズワルド」と「祝宴は田舎で」そして最後の「シチリアの月と花嫁」。「鉄道員オズワルド」の海の上に建っているかのような駅舎の家は、想像するだけで光溢れて「幸福」という捉えがたいものが幻のように浮かんでいるみたいです。「祝宴は田舎で」は、とにかく美味しい料理がこれでもかと押し寄せる贅沢な時間。そして、「シチリアの月と花嫁」は、映画の『ゴッドファーザー』を連想するような、痺れる一篇です。誰もが濃い血縁に結ばれた土地で、息を潜めるように日々を暮らす人たちの、ハレの一日です。この上なく清楚な美しい月の化身のような花嫁。その母の着る燃え上がるようなオレンジのドレス。ボルサリーノ帽にダークスーツの男たち。夜の中に浮かび上がる舞踏会・・招待の言葉は「あなたの来年の九月二十五日の予定は、私がお預かりしますが、よろしいか」。そのセリフを見事に形にして見せるイタリア男の実力に、くらっとしました。ずっとケばかりでハレのない私の人生(笑)一生縁のない特別な経験を共有させてもらえるなんて、なんて読書って美味しいんでしょう。この世のどこかに、そんな時間が、空間がある。そう思うだけで、とても豊かな気持ちになれる、素敵な一冊です。
2012年11月刊行
小学館
by ERI







