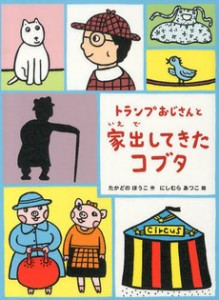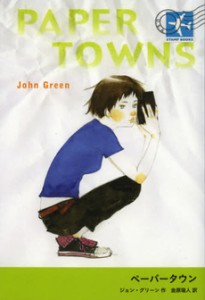昨日、関西では久々に震度6の地震がありました。私の住んでいるところでは、震度4くらい。阪神淡路大震災以来の久々の長い揺れでした。時間帯が同じくらいだったのも手伝って、あの記憶が一気によみがえりました。何年経っても、恐怖の記憶というのは体と心の奥底に潜んでいて無くなりはしないのだと、しみじみ実感し・・・東北の方々が延々と続く余震の中で、どんな気持ちで毎日を送ってらしたのかを改めて思いました。
昨日、関西では久々に震度6の地震がありました。私の住んでいるところでは、震度4くらい。阪神淡路大震災以来の久々の長い揺れでした。時間帯が同じくらいだったのも手伝って、あの記憶が一気によみがえりました。何年経っても、恐怖の記憶というのは体と心の奥底に潜んでいて無くなりはしないのだと、しみじみ実感し・・・東北の方々が延々と続く余震の中で、どんな気持ちで毎日を送ってらしたのかを改めて思いました。
この物語は、3.11をテーマにした連作です。あれから2年と少し経ちました。3.11については夥しい数のドキュメントや資料があります。ツイッターやブログというネット発信を含めると、それはそれは膨大な量になるはず。でも、3.11が物語として語られるのは、これから何だと思うのです。なぜ物語として語られなければならないのか。それは、物語が記録では見えないものを語るものだから。私たちが失ったもの。あの日からずっと心の中に鳴り響く声。闇から吹き上げる風、苦しみの中から見上げた空の色・・・それらをもう一度手繰り寄せて、失ったものを失ったままにしないために、心に深く刻んでいく営みが、「物語として語る」という行為です。そして、池澤さんのこの物語は、その出発点のような役割を果たすものなのかもしれないと思うのです。
この「双頭の船」は寓意的な手法を使って描かれています。物語を経るごとに大きく膨れ上がっていく船。200人のボランティアが舞台の上の書き割りのようにどっと移動し、甲板の上には瞬く間に240戸の仮設住宅が立ち並ぶ。そこには生きている人と、あの日にいなくなってしまった死者たちが同時に存在し、オオカミたちが命のオーラを放ちながら徘徊し、傷ついた犬や猫たちがつかの間の休息ののちに、あの世に旅立っていく。私は物語をたどりながら、なぜ池澤さんが、この物語の舞台を「双頭の船」にしたのか考えていました。この船のイメージは、間違いなくノアの箱舟でしょう。大昔に押し寄せた洪水の記憶が、人々の集まりの中で、もしくは子どもたちに語る枕辺で何度も何度も繰り返されて一つの共通の記憶となっていく。神話には、民族の心を同じ記憶に重ね、共有していくという無意識の意志が働いているはず。それは物語というものの在り方の原点だと思います。
「小説にもまた同じような機能がそなわっている。心の痛みや悲しみは個人的な、孤立したものではあるけれども、同時にまたもっと深いところで誰かと担いあえるものであり、共通の広い風景の中にそっと組み込んでいけるものなのだ」 (※)
これは、村上春樹氏の言葉ですが。物語は、たった一つの心に寄り添うもの。この世でたった一つだけの命に向き合おうとするものです。たとえば、去年レビューを書いた朽木祥さんの「八月の光」のように。「八月の光」はヒロシマの原爆をテーマにした物語です。それは、忘れ去られようとする「個」を徹底的に描くことで普遍へと繋げようとする、真摯な営みでした。鮮烈な記憶が時を超えて立ち上がります。それに対してこの「双頭の船」は、寓意的な手法を使って描かれています。登場人物たちも、どこかひょっこりひょうたん島の登場人物のように、実在の人物というよりは、キャラクターのような感じです。これは―私が勝手に思うことなんですが。3.11の東日本大震災を語る営みは、まだ始まったばかりです。「個」にリアルに向き合う物語を、今東北の方々が読むのは、きっと辛すぎる。だからこそ、ノアの箱舟という心になじみ深い神話を重ねることで、池澤さんは何とか道を開き、3.11を物語として語る回路をここから開こうとされたのではないか。この物語は、神話という原始的な物語の力を借りて、「個」に向かおうとした、営みなのではないか。そう思うのです。圧倒的な力になぎ倒されたたくさんの心たち、この世界から旅立ってしまった命に、何とかして寄り添おうとする営み。残されたものの痛みを共に感じ、分け合っていこうとする切なる願い。
平らになった地面はまるで神話の舞台のように見えたけれど、そこではまだどんな神話も生まれていない。この空っぽの場所の至るところに草の種みたいな神話の種が埋まっているのが見える気がした。(本分より)
何とかして希望の種を、あの空っぽになってしまった海辺に播こうとする、作家としての真摯な挑戦を、私はこの物語から感じました。だから、この「双頭の船」は、過去と未来を繋ぐもの、何度も何度もなぎ倒されながらもここまで歩いてきた過去と、これからを生きていこうとする未来を行き来しながら希望を運ぼうとする、私たち人間の営みという大きな流れを旅する船なのだと思うのです。神話と土の匂い。心の奥深いところから様々なシンボルが立ち上がり、トーテムポールのように各々の物語を語る。その声の語り部になってしまったような池澤さんの筆が冴える一冊でした。
※「おおきなかぶ、むずかしいアボガド 村上ラヂオ2」 村上春樹 大橋歩画 マガジンハウス
 この本、絵がとても素晴らしいのです。表紙の女の子、主人公のミレットの表情に思わず引き込まれてしまう。きゅっと結んだ唇と真剣な眼差し。強い風の中で踏み出していく一歩目の緊張と勇気が伝わってきます。
この本、絵がとても素晴らしいのです。表紙の女の子、主人公のミレットの表情に思わず引き込まれてしまう。きゅっと結んだ唇と真剣な眼差し。強い風の中で踏み出していく一歩目の緊張と勇気が伝わってきます。