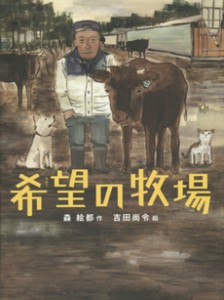何年ぶりだろう、インフルエンザにかかってしまった。くたくたなのだが、頭の芯にしこりのようなものがずっとあって眠れない。熱のせいと、ここ数日ずっと報道されているイスラム国による誘拐事件のことが頭から離れないせいだ。人質になっている本人とご家族の恐怖と孤独はいかばかりだろうか。湯川さんはもはや殺されてしまったのだろうか。赤ちゃんを産んだばかりという後藤健二さんの奥様がどんな思いで夜を過ごしてらっしゃるかを想像すると、とにかく一刻も早く救出して欲しいと心から思う。後藤さんは戦地の子どもたちを取材し、世界に発信していた人だ。日本ではこういう時にすぐ自己責任論を持ち出す人がいるが、私たちが戦地の実情や悲惨さを知り得るのは、彼のようなジャーナリストが報道してくれるからこそなのだ。どうかご無事で、と祈るように思う。
何年ぶりだろう、インフルエンザにかかってしまった。くたくたなのだが、頭の芯にしこりのようなものがずっとあって眠れない。熱のせいと、ここ数日ずっと報道されているイスラム国による誘拐事件のことが頭から離れないせいだ。人質になっている本人とご家族の恐怖と孤独はいかばかりだろうか。湯川さんはもはや殺されてしまったのだろうか。赤ちゃんを産んだばかりという後藤健二さんの奥様がどんな思いで夜を過ごしてらっしゃるかを想像すると、とにかく一刻も早く救出して欲しいと心から思う。後藤さんは戦地の子どもたちを取材し、世界に発信していた人だ。日本ではこういう時にすぐ自己責任論を持ち出す人がいるが、私たちが戦地の実情や悲惨さを知り得るのは、彼のようなジャーナリストが報道してくれるからこそなのだ。どうかご無事で、と祈るように思う。
先日見たこの映画は、紛争地帯を取材する戦争カメラマンの女性が主人公だった。しかも、冒頭のシーンは中東での自爆テロへの潜入取材から始まるのだ。死を覚悟して生きながら葬儀もすませ、しなやかな若い体に爆弾を巻き付けて車に乗る女性。主人公のレベッカは、彼女に、彼女を見送る同士たちに、刻々とカメラを向けてシャッターを切る。静謐な死の気配の中で、そのシャッター音だけが響くのだ。これから死のうとする人にまっすぐレンズを向けシャッターを押す、ためらいなく押し切る。そのプロとしての覚悟と胆のくくり方を、ジュリエット・ビノッシュは見事に演じていた。その根底にあるのは、理不尽な暴力や死に対する強烈な怒りであり、使命感なのだが、この映画ではカメラマンの本能のようなものをもう一つ掘り下げて描いてある。その本能に抗えないほど骨の髄までカメラマンである女性を演じきったジュリエット・ビノッシュが素晴らしかった。 スーザン・ソンダクは『写真論』の中で「写真を撮るということは、他人の(あるいは物の)死の運命、はかなさや無常に参入するということである」と述べていた。写真を撮るということは、時を止めることだ。動いているものも、呼吸しているものも、本来なら移ろうものを固定化する。撮った瞬間、映像になって切り取られるものは、もはやこの世界には無いものなのだ。目の前に常に強烈に生と死が輝いていて、それを客観的に切り取れる人だけがカメラマンの目を持っているのだと私は思う。写真というものが、何とも言えずに生々しく、壺のような静物を撮ってさえ時にエロチックであるのは、そこに常に死があるからだ。レベッカは、自爆テロに向かう女性の乗る車から降り際に、危険だと知りながら群衆の中で彼女の写真を撮ってしまう。それが引き金になってその場所で爆発が起こり、その場にいた人たちをレベッカも含めて巻き込んでしまう。若い女性が自爆テロ犯になる残酷さを撮るためだけなら、もう十分なほどシャッターを切っていたにも関わらず、テロ犯の女性の面差しに魅入られるようにシャッターを押してしまう。その本能が死に結びついていく凄惨さ。そして、そのカメラマンが母であり、妻であるということが、よりその凄惨さを際立たせてしまうのだ。他人の不幸にカメラを向ける、その残酷さを、この映画はまっすぐ見つめようとする。
レベッカは夫から、常に危険と共に生きることに耐えられないと最後通告を受ける。彼女の家庭のあるアイルランドはそれはそれは穏やかに美しい場所だ。優しい夫と可愛い娘たちのために、レベッカは一旦カメラを捨てようとする。しかし、安全だからという触れ込みで長女を連れていったケニアでいきなり動乱に巻き込まれ、レベッカは長女を置いてカメラを構え、争いの中に突入してしまう。本能に抗えなかったのだ。群衆になぎ倒されても前を向いてシャッターを押し続けるジュリエット・ビノッシュは、まさにカメラマンそのものだった。結局家を追い出され、全てを捨てて、またレベッカは戦場に向かう。しかし、また冒頭と同じ自爆テロの潜入取材の場面となるラストでまた監督はもう一つどんでん返しを用意する。今度のテロ犯が自分の娘と同じ年頃の少女であることを知ったレベッカは、今度はシャッターを切ることが出来ないのだ。何度試みてもどうしても出来ないまま、レベッカが地面の上にカメラを持って崩れ落ちるところで、映画は終わる。
戦争や饑餓などの凄惨な苦しみを撮影することには、常に人道的な議論がある。人の中に残酷なものをみたいという欲望があることも、その議論をややこしくする。写真を撮ることは傍観者であることでもある。冒頭の静謐な沈黙の中に響くシャッター音は、その残酷さを静謐な中に響かせる。プロである彼女にとってテロ犯は「被写体」なのだ。しかし、最後にレベッカはテロ犯を自分の娘と重ねてしまった。その瞬間、テロ犯の少女は見知らぬ被写体ではなくなってしまった。名前と顔と体温を持つかけがえのない存在になってしまった。もはや彼女は傍観者ではない。少女に心を寄せたその瞬間レベッカは、目の前で奪われようとする命の理不尽さに、その重みに改めて押しつぶされてしまったのだ。一枚の写真。そこに映っている眼差しと向き合うことの苦しみを、この映画は観るものに投げかける。
テレビをつければそこにある後藤さんの写真に、こちらを見つめる眼差しに、私もただ打ちひしがれている。こんな世界の片隅でブログを書いているだけの私に、何が出来ようか。ただ、彼の苦しみを思うしかない。想像するしかない。見ているしかない。手を差し伸べようもない。写真を撮るものの残酷さを、その写真を見るものは常に共有しているのだ。でも、だからこそ、見ないふりをするのではなく、自らの残酷さも含めて、目をそらさず見つめようと思う。自分の家族も救えないちっぽけな私であるけれど、なぜ、こんな写真が撮られることになったのか、もつれた糸の端がどこにあるのか、考えようと思う。地面に崩れ落ちたレベッカは、きっとまた立ち上がって写真を撮ると思うのだ。彼女は、今度は傷ついた子どもたちにカメラを向けていくのではないか。彼女が打ちひしがれたのは娘への、命への愛情ゆえなのだから。中東の子どもたちの苦しみを取材しようとした後藤さんも、何度も何度も打ちひしがれた人ではなかったのだろうか。そんな気がする。